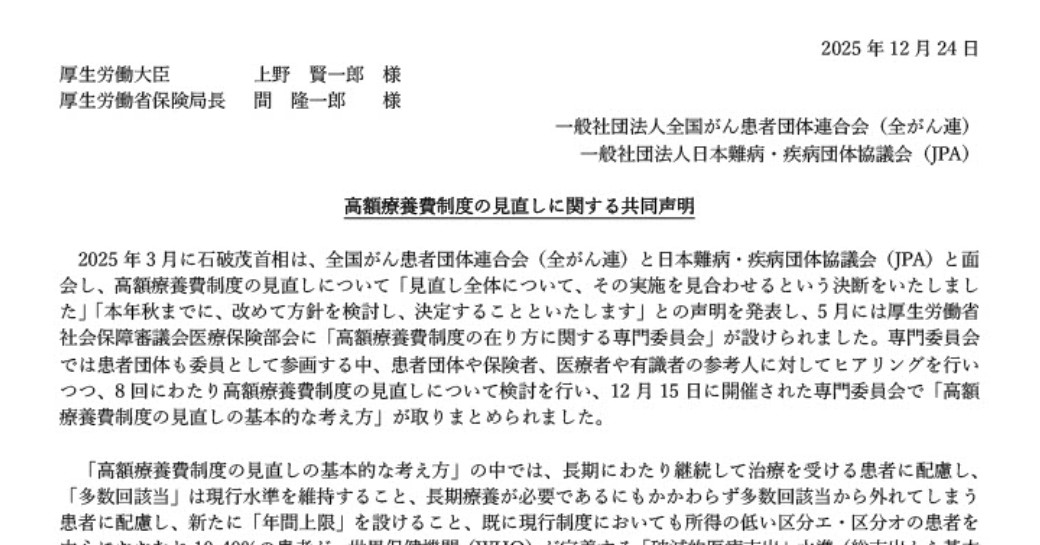おいしゃさんって元気になるためのみかただよ! 子供に病院や治療についてわかりやすく伝える『おいしゃさんにいくときの絵本』を出版
子供の頃、病院に行くのが楽しみだった人はいるだろうか? 怖くて、不安で、痛いことをされるところだとおびえていなかっただろうか?
安心して、納得してかかれるように、「教えて!ドクター」でもお馴染みの小児科医、坂本昌彦さんが監修した親子向けの絵本『おいしゃさんにいくときの絵本』(金の星社)が出版された。
幼い子供に、病気や病院、お医者さんや検査、治療についてわかりやすく伝える内容だ。
どんな思いで作った絵本なのか、坂本さんに取材した。

『おいしゃさんにいくときの絵本』を作った小児科医の坂本昌彦さん
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
嫌なことは嫌と言えて、わからないことは説明を受けるそんな子供の権利を守るために
——病院とかお医者さんって、子供は嫌なことをされるのではないかという不安を持っている場所や人だと思います。何のためにかかるのか、自分が何をされるのかあらかじめ伝えて、理解した上でかかってもらうための絵本でしょうかね?
そうですね。小児科の世界では以前から、「プレパレーション」と言って、子供が検査や治療を受ける前にその内容や流れを説明し、心の準備ができるような働きかけをしています。
何をされるかわからない状態でいきなり注射されたら、大人だって怖いですよね。だから、小児科では余計にそういう配慮が大事になってきます。

日本小児科学会の「医療における子ども憲章」
日本小児科学会も2022年に「医療における子ども憲章」というものを作っています。
1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
2. 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
3. 安心・安全な環境で生活する権利
4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
5. 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
6. 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
7. 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
8. 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
10. 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
こんな内容です。
ちなみに私が働いている佐久総合病院でも「こどもの権利」を2022年に同じように作っています。前の小児科部長がこういうことに関心があり、学会よりも先に作りました。

坂本昌彦さん提供
子供自身が知識を身につけることで自分や周りを守れる可能性
——どうしてこういう子供の権利を明記しようという流れになったのでしょう?
医療現場での子供の権利を守らなければいけないという話は以前から出ていました。
病気の子供は、親やお医者さんの言うことに従いなさいと言われがちです。でも、自分が受けている医療に対して、嫌だなと思ったら「嫌だ」など自分の気持ちをちゃんと出していいし、わからないことはちゃんと説明を受ける権利もあります。
僕たち小児科医は、どうしても保護者の方を向きがちですが、子供自身に向けたアクションも大事です。
また、子供自身が知識を身につけることで、子供自身や周りの友達の健康を守ることができます。
例えば、学校で友達がてんかん発作を起こして倒れた時、周りの友達がどうすべきか知っていたら、先生が来るまでにサポートができるかもしれない。寝かせて吐いたものが詰まらないように顔を横に向かせてあげるとか、楽な格好をさせるとか、そういったことができるだけでも全然違います。

出版した『おいしゃさんにいくときの絵本』
そんなことを伝える子供向けの絵本を作りたいなと思っていたら、たまたまお話をいただき、一気に話が進みました。
なぜ絵本?
——絵本という形がいいなと思ったのはなぜですか?
「教えて!ドクター」の精神でもありますが、元々、佐久総合病院では、医者が演説のように上から目線で伝えるのではなく、演劇のように楽しみながら理解してもらう住民への啓発活動を続けてきました。

坂本昌彦さん提供
自分は不器用なので、色々なアイディアを思いつくことができないのですが、「教えて!ドクター」のデザイナーの江村康子さんのアイディアで、イラストを使ったり、夏祭りでスタンプラリーのようなブースを作ったり、段ボールハウスを作ったりして、遊びを通じて伝えることを試してきました。

坂本昌彦さん提供
それと同じように、絵本を通じて楽しんでもらいながら伝えることは力強い啓発になるのではないかと考えました。
読み聞かせをしながら保護者も学ぶことができます。絵本を通じて親にも伝えることができるし、わかりやすければわかりやすいほど届きやすい。絵本ってすごくいいなと作りながら改めて思いました。

坂本昌彦さん提供
騙し討ちはダメ 不安を感じると、余計痛みも強くなる
——子供は検査も治療も何のためにするのかわからず、注射なんてなんでこんな痛いことをされるのか、不安や不満でいっぱいですね。先生も診療現場で子供に怖がられたり嫌がられたりしたことはありますか?
小児科医なら、みんな毎日のように経験していますよね。血液検査も、針を刺される前に心の準備が必要で、特に発達の特性がある子はそうです。
そういう特性がないお子さんでも、一般的に、お子さんの心の準備は大人より時間かかりますし、頭ごなしに「検査をやらなくちゃいけません」と伝えるだけでは不安が増すだけです。
もちろん、肺炎や胃腸炎などすぐに処置しないといけない場合はやむを得ないところもあります。でも定期検査や予防接種に関しては、できればあらかじめ親御さんになぜこの検査や注射をするのか説明してもらった方がいい。本人が納得したうえでやると、3歳や4歳であってもちゃんと我慢してくれるんですね。

『おいしゃさんにいくときの絵本』より
それがないと、時には脱走する子もいます。
一昔前だと、親御さんが騙し討ちをすることもありました。注射すると言うと病院に行きたがらないから、「今日は何もしないよ」と嘘を言って、いきなり抜き打ちで注射をする。そうすると子供は混乱しますし、不安な状態だと感じる痛みが強くなるという研究もあります。それこそ、HPVワクチンもそうでしたね。
やはり、なぜこの注射が必要で大事なのか説明して、納得し、安心してもらうことが大事です。
自分の症状を自分で伝える力
——この絵本では、病気はどういう状態なのか、それをお医者さんにどう伝えたらいいかも描いていますね。よく親御さんに症状を問診しがちですが、本人が伝えることも大事なのでしょうね。
自分の症状をどんな言葉で伝えたらいいか紹介するページについては、半分不安だったんです。すごく忙しい小児科外来の中で、子供自身に症状を伝えさせることを、他の小児科の先生方に受け入れてもらえるのだろうかと思ったからです。

『おいしゃさんにいくときの絵本』より
でも出版後、あるお母さんから、「子供自身が自分の言葉で症状を伝えることについて教えてくれる本はこれまでなかったので、すごくありがたかった」というコメントが寄せられました。それは良かったとほっとしました。
もちろん1から10まで全て子供が説明する必要はありません。背景や経過は、親御さんのほうがわかると思います。
一方、今、どれぐらい痛いのか、どんな風に痛むのか、どう症状が変化したかは、親御さんでもわからないところがあります。そういうことが本人の口から言えると、僕たち医者にとってもありがたいことなんですね。
——まさまざまな医療スタッフの役割とか、聴診器とかペンライトとかさまざまな道具も説明し、検査の内容についても説明しています。どんな人がいる場所かわかっていると、不安が和らぐわけですね。
そうですね。この絵本をいろいろな医療者にも勧めてもらいたいので、たくさんの医療職に登場してもらいました。
また、僕らも一応、どんな検査を、何のためにやるかは、お子さんに説明するようにしています。ただ、どうしても診察時間は限られるので、詳しい説明は看護師さんの方からしてもらうことが多い。
あらかじめ、こういう道具があって、こういう検査や処置をしているんだなと知っておくと、初めて聞くよりも、話が入っていきやすいかなと感じています。だから検査の項目も入れたんですね。
——小児科の先生って、聴診器を充てる時「もしもしするね」と言ったりして、すごい子供に伝わりやすいなと思っていました。お医者さんが体と対話し、体の中の情報を聞き取っているんだと言うことをすごくわかりやすい言葉で表現されています。何のためにやっているか伝わると、検査にも協力的になってくれるのでしょうか?
やはり、何のためにやるのか理解できなかったら、なぜそれに協力しないといけないのかと思うのは大人だって同じと思います。子供を尊重するという意味も当然ありますし、翻って、自分たち医療者も楽になる、色々とスムーズに進むのも大きなメリットです。そんな実利的な意味も大きいです。
注射は4ページも イラストも看護師さんの意見を聞いて工夫
——注射については4ページを割いてその流れやなぜ痛いのか、なぜ注射をしなければいけないのか丁寧に説明しています。やはり普段の医療処置の中で子供にとって一番怖いものだからですかね。
そうですね。子供たちが1番やっぱり怖くて心配な処置と言ったら針を刺すことだと思うので、ここは丁寧に描きました。
この中に注射をされているイラストがあるのですが、最初はわーんと泣いている絵だったんです。ゲラができた時に、僕は最初スルーしていたのですが、小児科外来の看護師さんが、「このわーんって泣いてる絵を見たら、余計怖がっちゃう子もいるんじゃない?」と指摘してくれました。

確かにそうかもしれないと思ったのですが、笑っているのも違うなと思ったので、間を取って、グッと我慢している表情にしたんですよね。
——絵もそんなふうに工夫されたんですね。他に工夫されたイラストはありますか?
迷ったのは、登場人物にマスクをさせるかどうかです。マスクをつけさせると表情が見えなくなっちゃうんですよね。子供むけの絵本だしマスクは取った方がいいかなとも思ったのですが、今、医療機関では基本的にみんなマスクをしています。外した絵を載せると、医療者側から、「なんでマスクしてないんですか?」と言われると思いました。
結局、一つひとつ、このイラストはマスクをつけるか、取ってもいいか確認していきました。そこは、コロナ以降ですから余計に気をつけたところです。
あとは、項目の話ですが、薬のページでは、飲む薬だけではなく、貼るものや吸入するものなど、さまざまな形態の薬を紹介しています。
症状も前向きな側面を紹介
——後半、もちろん咳や鼻水、熱などは不快な症状なのですが、ネガティブな面だけでなく、ばい菌を出すためだとか、病気と戦うためだとか、体の防御反応としてのポジティブな側面も紹介していますね。こうした面も伝えようと思ったのはなぜですか?
不快な症状を軽くするのはもちろん必要なのですが、体の反応には一つひとつ理由があることを小さい頃から知ってもらうことが、大人になってからの科学的なものの理解には繋がると思うのです。だから、変に病気や症状を怖がってほしくないし、症状一つひとつに理由があるんだと知ってほしい。

『おいしゃさんにいくときの絵本』より
熱が出ることにも、咳、鼻水が出ることにも理由がある。それを知ることで、自分が体調が悪い時に、「なぜ自分がこんな目に遭わないといけないんだ」ではなく、「自分の体の中の白血球さんが頑張ってくれてるんだ」と理解できれば、自己治癒力を応援するために、お水をしっかり飲んでちゃんと寝ようと前向きな療養につながるんじゃないかなと思います。
——最後は入院について触れています。なぜ家族や自宅から離れなくちゃいけないのか、理不尽な気持ちになる子もいると思うのですが、病院に泊まって治療を受ける理由もしっかり説明していますね。
手術についてはどこまで踏み込むか迷ったのですが、本格的に説明しようとしたらこれだけでは足りない。切ったり、血が出たりしているところは見せないイラストにして、あまり怖いイメージを植えつけないようにしようと、あっさり紹介するにとどめました。
親に向けてのメッセージや文章もしっかりと
——それぞれのページに「おうちの方へ」と保護者への補足の説明が入り、最後には感染予防策や薬、水分補給の重要性についてもしっかり書かれていますね。
この絵本は保護者にも情報を届けたいという思いが強いので、そこはおまけではなく、自分たちの中ではメインコンテンツの一つです。
——ステロイドや抗菌薬など誤解されがちな薬についてもしっかりと触れて。

やはり不安になりやすい部分を取り上げないといけません。ステロイドや抗菌薬もその一つですね。
——だいたい何歳ぐらいのお子さんと親御さんを想定して作ったのでしょう?
読み聞かせをして読んでもらう未就学児から小学校低学年ぐらいまでかなと思っています。実際に小児科外来に置いて、読んでくれるのはそれぐらいの子ですね。
2歳ぐらいまでは正直理解するのが難しい。それでも「ちゃんとお注射頑張ろうね」などの声かけをやっているご両親もいると思います。でも、あらかじめこういう絵本で理解した上で注射を受けるのは、やはり3歳を過ぎたあたりからでしょうね。
お薬を飲むのもそうです。薬が結構苦手なお子さんはいるのですが、2歳ぐらいまでは「苦いけど頑張って飲もう」とはなりづらい。だからゼリーやアイス、チョコレートクリームなどでごまかして飲んでもらいましょうとアドバイスをします。
でも、3歳を過ぎると理解できるようになってくるので、ごまかそうというよりは、なんでこのお薬が大事なのか理解してもらって、褒める。ちゃんと飲めたり、注射が打てたりしたらシールをあげるよとか、ご褒美をあげながらやっていく。やはり3歳ぐらいが境目かなと思います。
——この絵本をどんな風に役立ててほしいですか?
この絵本を読むことで、病院がどんなことをする場所なのかについて、お子さんが理解し、少しでも親しみをもっていただけたらと思います。保護者の皆さんがこどもに声かけするときのヒントもたくさん載っていますので、ぜひご活用いただけると嬉しいです。

坂本昌彦さん提供
【坂本昌彦(さかもと まさひこ)】佐久総合病院佐久医療センター 小児科医長
2004年、名古屋大学医学部卒業。愛知県や福島県で勤務した後2012年、タイ・マヒドン大学で熱帯医学研修。2013年ネパールの病院で小児科医として勤務。2014年より現職。専門は小児救急、国際保健(渡航医学)。所属学会は日本小児科学会、日本小児救急医学会、日本国際保健医療学会、日本小児国際保健学会。小児科学会専門医、熱帯医学ディプロマ。
日本小児科学会広報委員、日本小児救急医学会代議員および広報委員。日本国際保健医療学会理事。現在日常診療の傍ら保護者の啓発と救急外来負担軽減を目的とした「教えて!ドクター」プロジェクト責任者を務める。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績