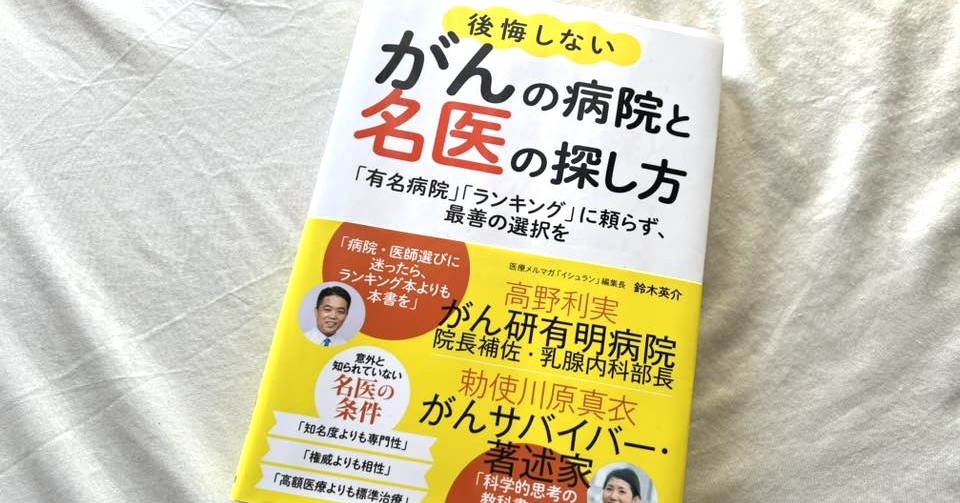東京都が費用助成を発表した無痛分娩 安全に広がるか?
東京都が10月から最大10万円の費用を助成すると発表した無痛分娩。麻酔を使って、出産時の痛みを和らげる方法だ。
この政策は、無痛分娩が安全に広がる原動力となり得るのだろうか?
日本産科麻酔学会副理事長で、昭和大学医学部麻酔科教授の加藤里絵さんにインタビューした。

「安全性が一番大事」と話す加藤里絵さん(撮影・岩永直子)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
無痛分娩とは?
——まず、無痛分娩とはどういうものなのですか?
経膣分娩中の痛みを麻酔を使って和らげる分娩方法です。代表的な方法として、「硬膜外鎮痛」と、「点滴からの鎮痛薬投与」の二つがあります。
腕の静脈から点滴で麻酔薬を入れる方法では、効果が穏やかで、お母さんや赤ちゃんが眠くなったり呼吸が弱まったりする可能性もあります。今回の東京都助成金では、点滴からの鎮痛薬投与は対象になりません。
硬膜外鎮痛の方が痛みを抑える効果も高く、お母さんや赤ちゃんが眠くなることもないので、多くの国で第一選択とされているのは「硬膜外鎮痛」です。
硬膜外鎮痛では、硬膜外腔という背中の脊髄の近い場所に、局所麻酔薬という薬と、多くの場合それに医療用麻薬を加えたものを投与します。

日本産科麻酔学会
——「無痛」と言っても痛みが完全になくなるわけではないですね。
なくなる時もありますが、無痛分娩を始める前には痛くなっていることが多いと思いますし、始めてからも痛みが出てくることはあります。
——ある程度、お産が進んで子宮口が開いてからやる施設も多いようですね。
施設によって違います。妊婦さんが「痛み止めを入れてください」と言ったらすぐに始める施設もあります。
ただ、どうしても分娩の進行を妨げる方向に働きやすいので、お産が進むまで少し待ちたいなと考える産婦人科の先生はいらっしゃるでしょう。
しかし、自然に陣痛が始まっている妊婦さんだったら、いつから始めても分娩時間はそんなに変わらないという文献も海外から出ています。でも海外と日本とは分娩を進めるために使えるお薬の量なども含めて違う面もあるので、一概には言えないです。
——今回、東京都が無痛分娩を希望する妊婦さんには最大10万円の助成を行うことが発表されました。だいたいいくらぐらいかかるのですか?
施設によっても違いますが、平均すると12万、13万円ぐらいでしょうか。
——それで10万出してもらえるなら大きいですね。
無痛分娩の要望は、間違いなく増えるのかなと思います。
安全管理のための「自主点検表」を満たす施設が登録
——東京都に登録する医療機関ということですが、どういう施設が登録できるのでしょう?
正式な発表はこれからだと思いますが、私が受けている説明の範囲では、「この基準を満たしてください」という施設基準を都が作っているところです。その基準を満たした施設を助成金の対象とし、今後施設から東京都に届出をしてもらうのだと思います。
——安全に行うための設備や人員配置の基準になりそうなのでしょうか?
「自主点検表(無痛分娩取扱施設のための、「無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言」に基づく自主点検表)」というものがあります。
2017年に無痛分娩の事故で母子が亡くなったり、お母さんが脳障害を起こしたりしたことが明るみに出て、安全対策を話し合うために厚生労働省の研究班が立ち上がりました。その研究班が作った提言をもとにした施設の「自主点検表」というチェックリストがあって、それを今、JALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)が管理しています。
この自主点検表の条件を満たすことは、登録要件の一つに入っているようです。そして無痛分娩で不具合が起こった場合には、都や関連団体に報告することになると思います。
半年で9500件という見込み 無痛分娩は増えない?
——東京都は初年度は10月から助成を始めて、半年で9500件の利用を見込んでいます。この見込みについてはどう思いますか?
昨年の東京都の無痛分娩数は2万件ぐらいです。半年では1万件ぐらいなはずで、東京都の利用見込みでは増えない計算になりますよね。
——確かにそうですね。
記者会見で小池百合子都知事は、都民の6割ぐらいが無痛分娩を希望していることを明らかにしました。希望があっても値段が高いから諦めている人が多いようです。また希望しない人の中にも値段が高いからという方もいらっしゃいます。助成があったら今の2倍ぐらいに増えそうな気がします。
しかし、急に2倍増えたとしても、医療側に供給できる余裕はありません。
——東京都の分娩施設の現状からして、無痛分娩が大幅に増えても医療施設は対応できないのですか?
少なくとも倍増は無理だと思います。
——なぜでしょうか?
これまでやっていなかった医療なので、それを急に増やしてくださいと言っても、機材も足りないし、人材も足りない。特に人材不足が深刻です。
——機材としては何が必要なのですか?
母体の状態を観察する生体モニターがまず必要です。継続して血圧や心電図などを測るための機材です。他に薬剤を入れるためのポンプなどです。
そもそも足りない麻酔科医、無痛分娩以外にも増えるニーズ
——そして肝心の人材です。無痛分娩には、もちろん麻酔科医が必要ですが、これに限らず、そもそも麻酔科医は不足していますよね。
麻酔科医は今も足りません。微増はしているのですが、同時に手術件数も増えてきていますし、手術以外の麻酔科医の業務も増えています。
集中治療、ペインクリニック、緩和医療などは昔からありますが、最近は医療の質の向上を求める声の高まりで、手術室外で内視鏡検査のために鎮静(麻酔で眠らせる)をしたり、お子さんがじっとしていないといけない検査をしたりする時にも麻酔が必要です。
心臓のカテーテル治療も手術室外でやることがあって、そういうところでも麻酔科医が必要です。新型コロナウイルス感染症では集中治療科医が活躍しましたが、集中治療室でも麻酔科医の仕事があります。
だから麻酔科医の数が増えても、不足し続けているのです。
——内視鏡の検査では、内視鏡を操作する内科の先生が鎮静をかけたりしていますね。
本来は、内視鏡の操作をする先生に加えて、鎮静薬の悪い影響が出ないように患者さんをしっかり観察する人を配置する必要があります。
産婦人科医や助産師も必要だが不足
——また無痛分娩は麻酔科医だけでやれるわけではなく、助産師さんや看護師さんらも必要ですよね。そのスタッフも不足していると聞きます。
そのほかに、もちろん分娩を管理する産婦人科医も必要です。
無痛分娩をするためには、「分娩管理」と「鎮痛管理」をすることが必要です。無痛分娩は痛みが和らぐだけの「普通のお産」ではないのですよ。
硬膜外鎮痛が分娩にも影響を与えますし、硬膜外鎮痛自体の合併症や副作用への対策をすることも必要になります。どの仕事をどの職種がやるかは施設によって違いますが、産婦人科医、助産師は当然欠かせません。
麻酔科医がいても、いなくても、ぜひ麻酔の合併症や副作用への対処を万全にして臨んでもらえればと願っています。
——助産師さんは足りているのですか?
私がこれまで働いてきた施設では、助産師さんは少ないと感じました。麻酔科医も産婦人科医も不足しているので、医師の業務を助産師さんに渡して行きたいのですが、それも難しいです。
——助産師さんは実際の無痛分娩でどんな管理を行うのですか?
施設によって様々ですが、私の施設ではまず麻酔を始めて20〜30分ぐらい厳重にお母さんの観察をしてもらいます。チェックリストを見ながら、異常がないか監視する。その後も無痛分娩中は、30分〜1時間ごとにバイタルサイン(血圧、呼吸数、脈拍、体温など)や足がどれぐらい動くかのチェックや、痛みの程度の確認をしてもらいます。
産後も数時間おきに、足の動きが悪くなっていないかを観察してもらったり、次の日に頭痛が出ていないかを確認してもらったりしています。硬膜外鎮痛の合併症が出ていないかの確認です。
施設によっては、助産師さんが薬の投与をするところもあります。麻酔科医が急増することはないと思うので、分娩室で働く医師の指示のもとで麻酔の補助をしてくれる助産師や看護師が増えることが無痛分娩を増やすための鍵だと私は思っています。しかし、助産師や看護師も足りていません。
予算をつけて無痛分娩を急に増やしたいと思っても、医療スタッフ不足は急には解決できません。
無痛分娩の安全確保のために気をつけるべきこと
——気になるのは、安全の確保です。無痛分娩の場合、分娩管理に関わる産婦人科医さんや助産師さんは何に気をつけなければならないのでしょうか?
私は分娩管理を担当する者ではないので、詳しいことは産婦人科の先生に尋ねていただきたいですが、無痛分娩によってお産の進行が遅くなりがちなので、積極的にお産を進めるようなことが必要になることが多いことが知られています。例えば子宮収縮薬の使い方が増えたり、赤ちゃんがうまれるときに赤ちゃんの頭が出やすくなるような器械分娩が増えたりします。
——鎮痛管理の部分で気をつけなければいけないリスクは何ですか?
一番怖いのは合併症です。普通は起きないのですが、稀に起き、お母さんや赤ちゃんに大きな影響が出ることがあります。
無痛分娩の合併症の一つの「高位脊髄くも膜下麻酔」は、硬膜外のカテーテルが少し深いところに入ることで起きます。血圧が急激に下がったり、重症だと呼吸が止まったりする場合もあります。稀に体の中の酸素が足りなくなって、心停止を起こすことさえあります。
過去に起きた事故を検証すると、高位脊髄くも膜下麻酔が起こることを想定していなかったり、知識がなかったりして、適切な対応ができていません。呼吸停止しているかどうかは慣れていない人だとなかなか見つけにくい。見つけたとしても、人工呼吸を慣れていない人が適切な人工呼吸をすることはなかなか難しいのです。
そういう意味でも「高位脊髄くも膜下麻酔」が起きた場合に的確に対処できるかどうかは重要です。
さらにもう一つの合併症として、「局所麻酔薬中毒」があります。硬膜外腔に入れるはずの麻酔薬が血管の中に注入された場合や、麻酔薬の量が多すぎる場合、けいれんを起こしたり、心臓が止まるような不整脈が出たりすることがあります。この場合、治療薬の投与や人工呼吸などの処置を行います。
このように、安全な無痛分娩は誰でもできるものではありません。助成金によって、無痛分娩の知識や経験の足りない医療者が参入し、安全が損なわれることがないことを願っています。
(続く)
【加藤里絵(かとう・りえ)】昭和大学医学部麻酔科学講座教授、日本産科麻酔学会副理事長
1992年、千葉大学医学部卒業。同大麻酔科と関連病院で研修し、2000年、英国オクスフォード大学臨床医学部博士課程修了。千葉大学大学院医学研究院麻酔学領域、埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター周産期麻酔部門、国立病院機構千葉医療センター麻酔科、東京女子医科大学附属八千代医療センター麻酔科などを経て、2010年、北里大学医学部麻酔科学教室准教授、13年、同大医学部附属新世紀医療開発センター周生期麻酔学准教授を歴任。2018年より昭和大学医学部麻酔科学講座教授に就任した。日本産科麻酔学会副理事長、東京麻酔科医会東京都無痛分娩ワーキンググループ長などを務め、安全な無痛分娩の普及に尽力している。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績