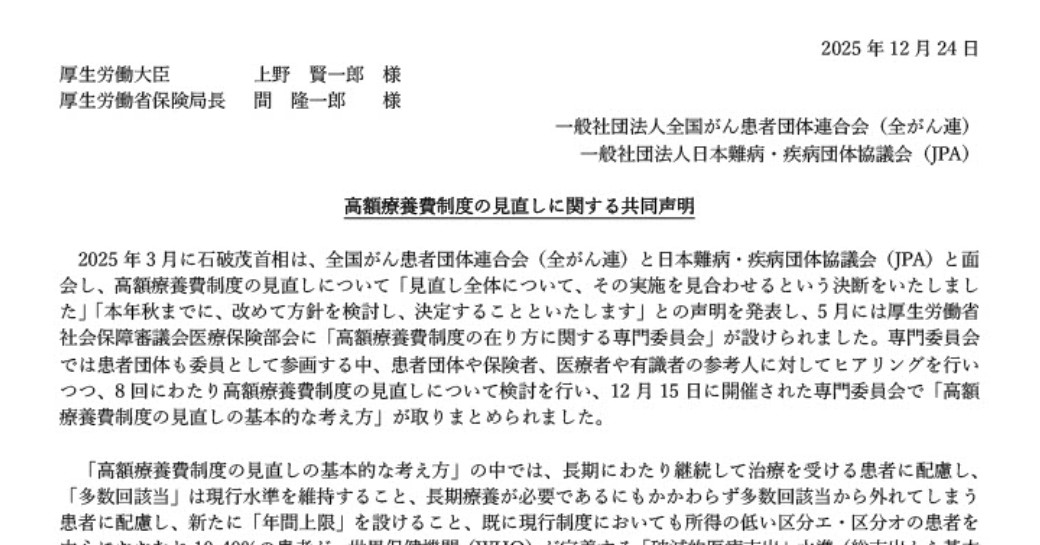参政党の医療公約「終末期の延命医療費の全額自己負担化」医療政策学者と検証する
参政党が参議院選挙で「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」という公約を掲げ、「誰が『終末期』や『過度な延命治療』を線引きできるのか?」「金のない人は苦しんで死ねというのか?」などと批判の声が高まっている。
「終末期における過度な延命治療に高額医療費をかけることは、国全体の医療費を押し上げる要因の一つとなっており」ともするが、この認識は正しいのか?
具体的には「胃瘻・点滴・経管栄養等の延命措置は原則行わない」としているが、これは医療政策としてどうなのか?
医療経済学や医療政策学の専門家で日本福祉大学名誉教授の二木立さんに取材し、検証する。

二木立さん(二木さん提供)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
繰り返される似たような言説
——2019年に、「終末期医療が医療費を圧迫している」として終末期医療を保険適用外にすることを提案した「落合・古市対談」について二木先生にインタビューした時に、同様の言説は繰り返されており、珍しくもないと評価されていました。今回の参政党の公約も同様の言説との印象を抱いたのですが、いかがでしょうか?
私も参政党の「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」等の公約が、2019年に落合・古市氏が述べたこととそっくりであることに驚きました。彼らも「(高齢者に)『最後の1か月間の延命治療はやめませんか?」と提案すればいい」、「終末期医療の延命治療を保険適用外にするだけで話が終わるような気もする」と言っていましたね。

参政党の公約より
それと同時に、私が当時、彼らの主張の誤りを批判して示した事実・データと考え方・ロジックが、ほとんどそのまま通じることも再確認しました。
このインタビューの読者もぜひそれを読んでいただきたいと思います。

ただし、6年前はあくまでも二人の個人の言説で、しかもそれがジャーナリズムとSNSの両方で厳しく批判され、落合氏は謝罪・撤回しました。古市氏は今でも頬被りしていますが。
昨年の総選挙時の玉木雄一郎・国民民主党党首の10月12日の党首討論会での「社会保障の保険料を下げるためには、我々は高齢者医療、特に終末期医療の見直しにも踏み込みました」という発言についても批判されて、あっという間に撤回しましたよね。
それに対して、今回は「全国政党」の公約でありながら、ジャーナリズムでの報道や批判はごく限られていること、そのために参政党もその公約を撤回していないことに、恐ろしさ・異様さを感じています。ただし、私はSNSはまったく使っていないので、それについての反応については分かりません。
私の調べた範囲では、全国紙では「しんぶん赤旗」が7月6日2面で「終末期医療は全額自己負担/参政党が異常な公約」と批判していました。
終末期の医療は、本人や家族の生き方に関わる問題で、政治家が口を差しはさむべき性格の問題ではありません。「全額自己負担化」導入は、経済的にゆとりのない人から「生きる尊厳」を国家が強制的に奪うものにほかなりません。
この批判は的を射ていると思いますし、私も賛成です。
朝日新聞も、この公約について参政党の神谷宗幣代表の説明を報じていました。撤回でも弁解でもありませんでしたね。
若い世代の「被害者意識」が煽られている
——なぜこのような言説は繰り返されるのか、先生のお考えを聞かせてください。
このような言説が繰り返される理由は多面的で、一言では言えません。
まず歴史的に言うと、国民医療費が急騰して医療保険財政、国家財政を圧迫するとの議論は、古くは1950年代の「結核医療費抑制論」が出発点で、75年前にはすでにありました。
他に有名なところでは、1983年の吉村仁氏(当時厚生省保険局長)の「医療費亡国論」、2015年「オプジーボ亡国論」など、長い歴史があります。枚挙にいとまがない。1980年代以降は、人口高齢化に伴って国民医療費のうち比重が増している高齢者の医療費が批判のターゲットになりました。
最近は、現役世代、特に20〜30代の若年世代の所得が伸び悩む一方、社会保険料は引き上げられているという「被害者意識」が、 ジャーナリズム、国民民主党や日本維新の会、さらには参政党の「煽り行為」もあり、強まっています。
それが世代間の分断、社会連帯意識の低下を生み、一見急騰しているように見える高齢者医療費への批判を強めているとも思います。
モノの生産やIT分野では、技術進歩・イノベーションによってモノ・情報の質は向上するが価格・費用は下がるのが一般的です。それと異なり、医療の技術進歩・イノベーションでは、効果は上がっているのですが、価格・費用も上がることが、一般にはほとんど理解されていないことも見落とせません。
これは参政党ではありませんが、日本維新の会が2月20日に発表した「社会保険料を下げる改革案(たたき台)」には、「他の産業と同様に、市場原理を働かせることで(医療・介護)サービスの質を上げながらコストを下げていく」とナイーブに書かれていたので、思わず私は笑ってしまいました。
もう一つ、特に若い世代は終末期、終末期医療のイメージが湧かないので、どんどん死んじゃうのだから無駄だと直感的に感じるのかもしれません。
政党がこうした公約を掲げるのは初めて 社会連帯意識の低下を招くことを危惧
——このような言説を政党が公約として掲げることはあったのでしょうか?
政党が公約として掲げるのは、間違いなく初めてです。参政党の2024年総選挙公約にもまったく書いてありませんでした。
昨年10月の総選挙の公約を読む限り、日本維新の会や国民民主党は、もう少しマイルド、抽象的な主張をしていました。参政党は、両党よりさらに「右」のスタンスを意識的にとっているので、医療についても、敢えてより「先鋭的」な、尖った主張をすることで、現役世代・若者世代の支持を集めようしているのだと思います。
——公党や政治家がこうした公約を掲げることについて、どのような影響があるとお考えですか?
私は、このような主張が、医療・社会保障についての世代間対立、社会連帯意識の低下をさらに促進することを危惧しています。
ちなみに、慶應義塾大学教授の権丈善一氏は、現在は(仕事の上で)現役・若者である人々も長期的には高齢者になり、医療・社会保障の給付を順繰りに受けるのだから、世代間の対立を煽る「現役・若者世代」という表現をやめ、中立的な「現役期・若者期」と呼ぶことを提唱しています。私もそれに賛成です。
高齢者一人当たりの医療費は増えているわけではない
——当該公約の前段に「70歳以上の高齢者にかかる医療費は年間22兆円と全体の半分程度を占め、特に85歳以上になると一人あたりでは100万円を超える。終末期における過度な延命治療に高額医療費をかけることは、国全体の医療費を押し上げる要因の一つとなっており」と書かれています。これは事実でしょうか?
第一文と第二文は全く異なります。
最初の一文「70歳以上の高齢者にかかる医療費は年間22兆円と全体の半分程度を占め、特に85歳以上になると一人当たりでは100万円を超える」は事実です。
しかしこれは、日本で人口高齢化が進行し、70歳以上の高齢者の実数が増加していること、また高齢者は「若人」(行政上は69歳以下の人々)に比べて有病率が高く、1人当たり医療費も高いための当然の帰結です。
ただし、1人当たり医療費の高齢者/非高齢者の倍率は、高齢者の定義をいくつにしても長期間少しずつ減り続けています。これはほとんど知られていません。ですから、高齢者の1人当たり医療費が急増しているわけではありません。
例えば、65歳以上/65歳未満では、2000年度は4.45倍だったのが、2022年度は3.70倍(775.9万円/209.5万円)(厚生労働省『国民医療費の概況』)に低下しています。
昔は70歳以上対70歳未満で見ており、国民医療費ではなく一般診療費で見ていました。その統計のスタートが1977年度で老人医療費がなかった時ですが、4.41倍でした。73年に老人医療費が無料化され、この70歳以上対70歳未満の倍率はどんどん上がって、ピークは86年度で5.67倍まで行きました。
その後は、高齢者の医療費抑制政策が始まったので、倍率は逆にどんどん低下して、今に至っています。
こういうことで、少なくとも老人保健法が成立した1982年以降は、老人医療費(70歳以降)は一般の医療費よりも厳しく抑制されてきました。
だから高齢者の数が増えているので医療費が増えていること、あるいは高齢者は元々病気がちだから医療費が高いことは事実ですが、一人当たりの高齢者が若人に比べて優遇されているわけでもなんでもありません。
終末期の医療が医療費を押し上げている、は事実誤認
そして、第2文「終末期における過度な延命治療に高額医療費をかけることは、国全体の医療費を押し上げる要因の一つとなっており」は、明らかな事実誤認です。
そもそも「終末期」の定義が示されていません。かつては「終末期」を死亡前1年間または6か月と広く捉えることが国際的にも一般的でしたが、これは広すぎます。1年前、半年前から死亡するかどうかはわかりませんから、あまり意味がないわけです。
日本では2000年以降は、マクロの医療費分析を行う場合は、死亡前1か月間の医療費に限定するようになっており、これの総医療費に対する割合は約3%にすぎないことが確認されています。
しかも、これには心筋梗塞や脳卒中等による急性期死亡の医療費も含まれており、常識的にいって終末期とは言えないでしょう。だから、これらを除いた「終末期」患者の医療費はさらに少ないはずです。私は1〜2%程度ではないかと見ています。
この結果を踏まえて、厚生労働省関係者も、すでに2001年に、「死亡直前の医療費抑制が医療費全体に与えるインパクトはさほど大きくない」「(終末期ケアが)医療費の高騰につながる可能性は否定している」と明言しています。(二木立『医療経済・政策学の探究』勁草書房,2018,第1部第6章「終末期医療」)。
私は当時、これをもって、終末期の医療費が医療費高騰の原因であるかどうかの政策的な論争は終わったと思いました。実際に厚労省はそれ以降、こうした議論をしていません。ただ、政治的には何度も何度も同じような主張が繰り返されています。
ちなみに終末期が死亡前1ヶ月、というのは、マクロの医療費分析を行う上での仮定です。現実の終末期は、個人間でも病気によってもものすごく差があり、一律には定義できないと思います。このことは、日本老年医学会の「高齢者の人生の最終段階における医療・ケアに関する立場表明2025」でも詳しく書かれています。
胃ろうは「多くの国民が望んでいない過度な延命治療」?
——公約では具体的に、「欧米ではほとんど実施されない胃瘻・点滴・経管栄養等の延命措置は原則行わない」と書かれています。これは事実でしょうか?また公約のタイトルに「多くの国民が望んでいない終末期における過度な延命治療を見直す」とありますが、胃ろう、点滴、経管栄養は「多くの国民が望んでいない終末期における過度な延命治療」であるのか、医学的に見ても不必要であるのか、ご見解を教えてください。
医療と医療保障のあり方は、アメリカとヨーロッパ・カナダ・豪州では相当異なるので、「欧米」という用語を使うのは不適切です。
その上で、ヨーロッパの多くの国では「胃瘻・点滴・経管栄養等の延命措置」はあまり行われていないのは事実のようです。
ただし、物事には両面があります。高齢者の「福祉」が日本に比べてはるかに充実していると言われる北欧諸国の高齢者「医療」は、日本的基準では非常に手薄く、高齢者差別になることが行われていることも見落とせません。
これは新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に日本でも紹介されたことですが、スウェーデンでは、75歳以上の高齢者のICU(集中治療室)への受け入れやECMO(体外式膜型人工肺)装着が制度的になされませんでした。(宮川絢子氏インタビュー=スウェーデン在住の医師・カロリンスカ大学病院泌尿器科勤務)「スウェーデン新型コロナ『ソフト対策』の実態。現地の医師はこう例証する」フォーブズ・ジャパン,2020。
6月27日に公表された日本老年医学会の「高齢者の人生の最終段階における医療・ケアに関する立場表明2025」は「立場1」で「年齢による差別(エイジズム)に反対する」と宣言しています。
続く、「立場2 緩和ケアを一層推進する」でも、「人生の最終段階における医療行為の適否の判断」で、このように明記しています。
「しかし、人生の最終段階における医療行為は、治すための医療行為を除外するものではない。予想しない急変時など、医療行為の効果の判断に不明な点がある場合は “time-limited trial(TLT)”を実施し、その効果を確認することが患者の生命を擁護するために重要である」
TLTは「立場表明2025年」で初めて用いられた概念で、6回も(肯定的に)言及しています。
(口で食事が取れなくなった患者が、胃に開けた穴から栄養を入れる)胃ろうについても同様の側面があります。とりあえずやらなければならない、という対応です。逆に言えば、とりあえず胃ろうを作って、必要なくなったら外す人もたくさんいます。永遠に続くわけでもなんでもないのです。
胃ろうについては、同じく「立場2」で、以下のように慎重に書かれており、決して否定していません。
長年、人生の最終段階における医療・ケアをめぐる課題であった胃ろうや経鼻胃管による経管栄養法を含む人工的水分・栄養補給法や、気管切開、人工呼吸器装着を含むあらゆる医療行為の適否の判断も、緩和ケアの視点から慎重に検討されるべきといえる。
私は「立場4 人権と尊厳および文化を尊重する意思決定支援を推進する」が、「『自律(autonomy)』を特に重視する英語圏諸国と異なる日本の文化的特徴」に言及しているのも、非常に重要と思います。
「自律(autonomy)」を特に重視する英語圏諸国と異なる日本の文化的特徴として、医療・ケアの意思決定に関する家族等の関与のあり方や、 「推し量る文化」のなかで他者に遠慮したり配慮したりして率直な自己表現を回避しようとする態度、また、専門職に決定を委ねようとする態度などが挙げられる。これは高齢世代において特に顕著ではあるが、同一世代でも個人差が大きいことから、あくまでひとりひとりについて本人の意思・意向を把握することが求められる。
参政党は「日本人ファースト」なんですよね?日本や日本人の文化的特徴を無視して、欧米の基準の機械的導入を求めることはちょっと疑問です。
また、参政党が「胃ろう、点滴、経管栄養は『多くの国民が望んでいない終末期における過度な延命治療』」と主張するのは独断かつ、それらを望むあるいは必要とする一定数の患者・家族の自己決定権を否定しています。
胃ろう・経管栄養については、高齢者を含めて健康人はとても忌避的意識が強いと思います。しかし、それをしなければ生きられない状況になった当事者・家族の意識・判断はまったく異なります。
胃ろうを国民は望んでいないのか?
日本では胃ろうが減っていると言っても、2016年以降も、胃ろう造設術は毎年新たに5万件実施されています(後述する井上雅博ら論文)。
日本では2010年前後に胃ろうバッシングが起こり、その急先鋒だった高橋泰さん(国際医療福祉大学教授)は2012年に、日本もフランスのように、今後胃ろうは急速に減少し、「2020年頃には高齢者に対する胃ろうがほとんど作られない状況が訪れる」との大胆予測をしました(「フランスの高齢者に対する胃ろうはなぜなくなったのか」『社会保険旬報』 2012年5月21日号(2496号): 12-16頁)。外れてますよね。
厚生労働省も胃ろうの乱用防止(禁止ではない)のために、2014年度の診療報酬改定時に、胃ろう造設術の点数の大幅引き下げを行いました。具体的には、10,070点から6,070点に4割も減点し、この点数変更と同時に、胃瘻造設時嚥下機能(飲み込む機能)評価加算(2,500点)を新設し、術前の嚥下機能評価を適切に行うことを推奨しました。これは適切だと思います。
当時は特別養護老人ホームでも胃ろうをつけないと入所を受け入れないとしている不適切なところがあったんです。
この直後、胃瘻造設術は激減しましたが、2016年以降は横ばいか一進一退が続いています(井上雅博・他「日本における終末期医療の変化-NDBの解析から」『厚生の指標』2025年4月号:22-26頁。Hattori Y, et al: National trends in gastrostomy in older adults between 2014 and 2019 in Japan. Geriatr Gerontology Int 2022 Aug 22(8):648-652)。
「胃瘻・点滴・経管栄養等の延命治療は原則行わない」との主張は決して新しいものではなく、一部の医師・論者が以前(20世紀末)からしていましたが、現在でも、それは少数派だと思います。
6月28日に開かれた日本医療政策学会第1回学術集会では、シンポジウム「重度認知症における胃ろうと中心静脈栄養-医療政策から考える」があり、私も参加しました。そこでも、胃ろうの有効性を前提にした上での真摯な議論がなされていました。
具体的には、訪問診療を行なっている佐々木淳先生が「本人の意思決定がとても重要なので、医者が強行採決し、一方的に胃ろうを作るとか作らないというのは、家族を傷つける。医師はコミュニケーション能力を身につける必要がある」と強調していました。
また、佐々木さんは「医療を必要とするような摂食嚥下障害のある人の胃ろう開始は、多くの場合急性なんだ」と話していました。いわゆる老衰するような人には、今はやらない。
厚労省の人生の最終段階における意思決定支援のガイドラインでも、患者や家族、医療者、医療者以外の関係者との対話のプロセスを非常に重視しています。
それに対して参政党は、「医師が即座に心の負担なく適切な判断ができるプロセスを徹底」と書いています。これは今の世の中の流れと完全に逆行しています。せっかくここまで、医療者が一方的に決めるのではなく患者や家族と一緒に合意形成するんだよと20年間積み重ねてきたのに、それをちゃぶ台返しすることになるのではないでしょうか。
なお、このシンポジウムでは、医ろうの費用(保険診療費、社会的費用)は高いとの主張は、演者と参加者の誰からも出されませんでした。
「終末期の点滴や人工呼吸器の診療報酬見直し」「全額自己負担化」はもはや戯言・妄言レベル
——参政党は他にも、「終末期の点滴や人工呼吸器管理等延命治療が保険点数化されている診療報酬制度の見直し」「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」などを掲げています。そもそも「終末期の」「過度な」延命措置医療は、定義できるものなのでしょうか?
これらの施策はもはや戯言・妄言のレベルで、今後も、現実の医療政策で論議されることはないでしょうね。「朝日新聞」(7月9日)によると、福岡厚生労働大臣は7月8日の閣議後会見で、終末期医療についての認識を問われ、「生命倫理に関わる問題とし国民的な議論が必要。慎重に検討すべき」と語ったと報じられています。これは、終末期医療のあり方に関する「議論」です。保険適用を外すなんて話はしていません。
私が、この点についての政治家の発言でもっとも見識があると思うのは、亡くなった安倍晋三首相2013年の発言です。
「尊厳死は、きわめて重い問題であると、このように思いますが、大切なことは、これは言わば医療費との関連で考えないことだろうと思います」(2013年2月20日参議院予算委員会。梅村聡議員の尊厳死法案法制化が必要との発言を受けての答弁)。
私が少し調べたところ、参政党の神谷宗幣代表は一時期、自民党の地方議員をしたこともあり、安倍首相の支持者でもあったそうです。今回の公約は、安倍首相の見識ある発言に反するものだと思いました。
若者ウケ狙い? しかし若者もいずれは高齢者になる
——他にもこの公約では「予防医療が医療費削減に貢献する」と書かれています。これは医療経済学の観点では否定されている内容ですよね?
予防医療の中で医療費を節減するものはあることはあるのですが、予防医療全体が減らすわけではなく、むしろ医療費を増やすものも多いことは医療経済学の常識です。安倍首相は予防医療にご執心でしたが、亡くなってからは政府も言わなくなっています。
決して私は予防医療を否定するわけではないです。国民の健康増進のためにやればいいのであって、それを医療費抑制と結びつけるからおかしな主張になるわけです。
——ワクチンなどへの懐疑的な姿勢も色濃く見られ、科学的根拠に乏しい内容が目立ちます。
参政党の内情は知りません。しかし、昨年日本維新の会と国民民主党の公約を分析する時に聞いたのですが、自由民主党は大きな政党で与党だから蓄積があり、集団で検討されています。それに対して、小さな政党は影響力のある議員や声の大きい議員が主張すると採用されるそうです。
参政党も誰か医療政策のブレーンがいるのかもしれませんが、医療政策全般への理解が不十分なまま、若者ウケするような政策を打ち出しているのではないかと想像します。
——神谷代表は記者団に遊説先で終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」を掲げたことの真意を問われ、「みとられる時に蓄えもしないと大変だと啓発する思いで入れた」と答えたそうです。自己責任論に見えます。
貧乏な人はちゃんと金を貯めなければいけませんよ、自立しなさい、という意味でしょう?胃ろうだけでも新規に受け始めた人が毎年5万人はいることを考えると、恐ろしい主張です。普通の成熟した政党であれば、与党であれ野党であれ全額自己負担なんて掲げませんよ。日本維新の会でさえこんなことは言っていません。
要するにウケ狙いだと思います。
—— NHKによる最近の政党支持率を見ると、参政党は公明党や共産党よりも高くなっていて、特に若い世代(18〜29歳 8.8%、30代 9.9%)での支持率が高くなっているのに驚きます。彼らの世代間対立を煽る作戦は成功していると考えていいのでしょうか?
これを見て私も驚きました。だけど今の若者だって、何十年か後には高齢者になるんです。未来の自分の首を絞めているんですよね。そこをわかっていないのではないかと思います。
【二木立(にき・りゅう)】日本福祉大学名誉教授
1947年生まれ。1972年、東京医科歯科大学(現・東京科学大学)医学部卒業。代々木病院リハビリテーション科科長、病棟医療部長、日本福祉大学社会福祉学部教授を経て、2013年日本福祉大学学長に。
2018年3月末、定年退職。『文化連情報』と『日本医事新報』に連載を続けており、毎月メールで配信する「二木立の医療経済・政策学関連ニューズレター」は医療政策を論じる多くの官僚、学者、医療関係者が参考にしている。
著書は、『コロナ危機後の医療・社会保障改革』『2020年代初頭の医療・社会保障』『病院の将来とかかりつけ医機能』(いずれも勁草書房)等、多数。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績