障害者を支援してきた弁護士がALSになった 日々できないことが増える身体で考えたこと
旧優生保護法違憲訴訟の共同代表も務め、障害者を支援する活動を続けてきた北海道小樽市在住の弁護士、西村武彦さん(69)。
昨年8月に、全身が徐々に動かなくなっていく難病、ALS(※筋萎縮性側索硬化症)と診断された。
日々できないことが増えていく中で、何を感じ、どう生きようとしているのか。
札幌市の事務所に訪ねていった私を、西村さんは歩いて出迎えてくれた。話すのも不自由はない。9月2日、ロングインタビューを行った。
※手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん動かなくなっていく進行性の神経難病。治療法がまだ見つかっていないが、人工呼吸器や胃に開けた穴から栄養を補給する胃ろうなどを作って長く生きられるようになった。体が動かなくなっても感覚や内臓機能などは保たれる。
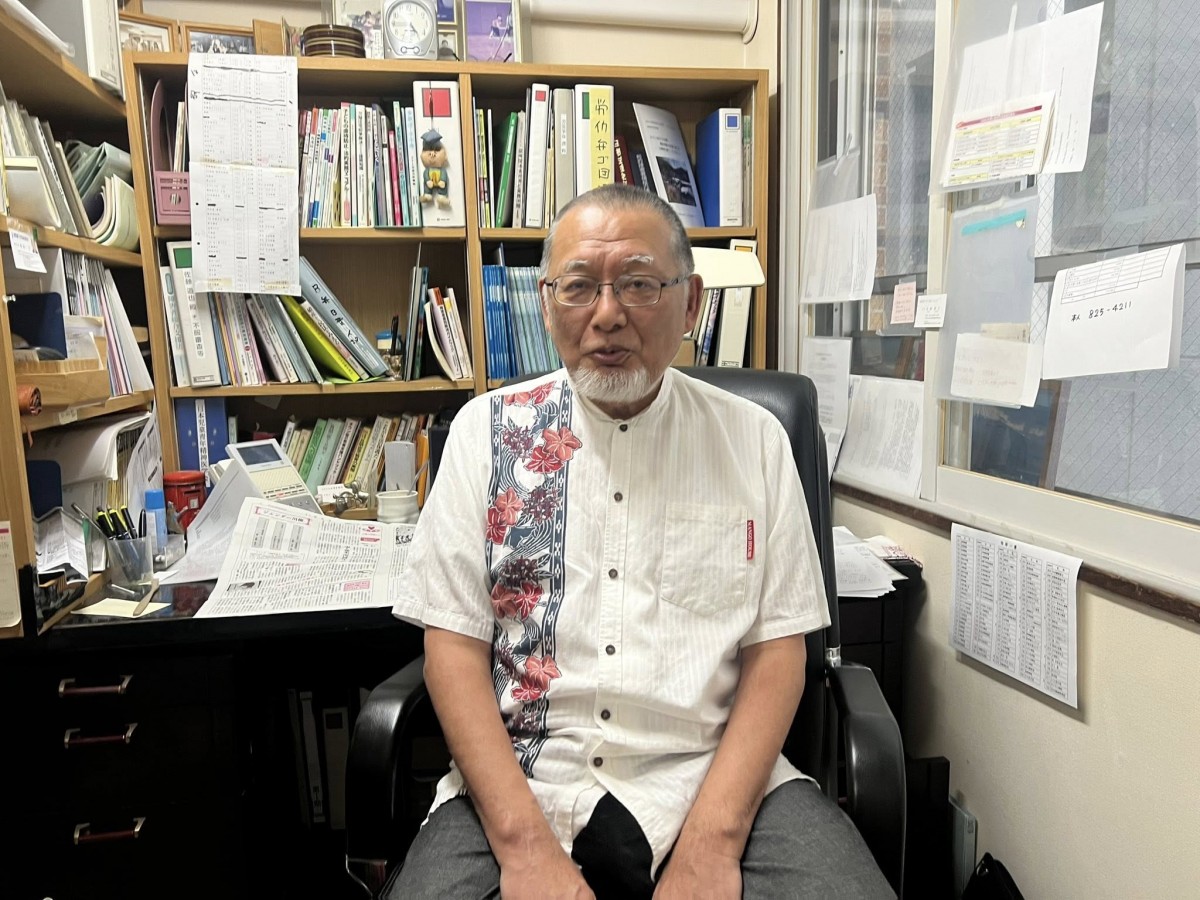
西村武彦さん。札幌市の事務所の自室で(撮影・岩永直子)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
飛行機でキャリーケースを持ち上げられず異変に気づく
異変に気づいたのは、昨年5月、いつものように東京出張に向かう飛行機に乗り込んだ時だった。
「いつも私はキャリーケースを持っていくのですが、飛行機に乗るとだいたい上の棚に入れるんですよ。ところが、いつもなら簡単に持ち上げられるのに、18キロか19キロかあるバッグを持ち上げるのになんだかすごい力がいる。その時は頭の上で支えながら持ち上げたのですが、6月に行った時に本も減らして軽くしたのに持ち上げられない。これは何か大変なことが起きているなと思いました」
そのうち、手を強く握ると開く時に力がいることにも気づく。振り返れば、昨年冬の終わり、自宅の雪かきをするのにスコップを持つ手が強張っていたことも思い出した。その時は寒いから凍えただけかと思っていた。
しばらく様子を見ていたが、裁判も少ない8月に入るとすぐに、近所の神経内科クリニックを受診した。似た症状がある患者の後見人業務をやっていて、なんとなく神経系の病気ではないかという目星をつけてのことだ。大きな病院に紹介され、10日間の検査入院をすることになった。
様々な検査をしながら、一つひとつ病気の可能性を探っていく。足の裏を引っ掻くような検査をしながら主治医が研修医に説明しているのを聞いて、ALSの可能性があることに気づいていった。
8月27日、主治医に「奥さんも呼んでください」と言われ、夫婦で確定診断を聞いた。
やはりALSだった。主治医からは「他の病院で検査し直していただいても」とセカンドオピニオンも勧められたが、「いえ、わかりました」と診断を受け入れた。検査の過程である程度、予測はしていたから、ショックはそれほど受けなかった。
ただ、70歳になったら訴訟からはほぼ手を引いて、障害者の就労を支援するために余市町に作った「就労継続支援B型作業所」の運営に仕事を絞るつもりでいた。その計画は考え直さないといけないなと、思っていた。
妻や子供は、自分の前では冷静に受け止めてくれて助かった。
裁判でこれまでにない大きなミス
「診断の時はあまりショックではなかったのですが、むしろショックは後から生まれてきたんですよ。裁判でミスってしまって......」
診断を受けた翌月か翌々月のことだ。
ある訴訟の和解条項で、重要な事項を見落として、依頼人に400万円もの損害を負わせることになった。ポケットマネーから、損害分を支払った。
「いろんな報告を受けていたのかもしれないけれど、頭の中ではきっとある部分がエアポケットになって、聞き逃していたんだと思います。心ここにあらずみたいな感じだったのでしょう。裁判で相手に有利になってしまうようなことを他にもやってしまった。そちらは、結果的にそれほど痛手にはならなかったのですが、これはまずいなと思いました」
30年の弁護士人生で、こんな初歩的なミスはおかしたことがない。
診断を受けた時から考えてはいたが、新規の案件はそこからほぼ取らなくなった。
「ALSという診断を受けて、『この病気は進行が早い』と言われますよね。裁判はどうしても受けたら、解決まで1年半や2年かかるから、基本的に受けなくなりました」
どんなふうに症状が進行していくか「ひなたぼっこ通信」を毎月配信
これまでALSやそれに似た病気について知識は持っていたつもりだが、やはりどこか他人事だった。自分がこれからどうなっていくのか知りたくて、関係する本を読みあさっていった。
「最初に読んだのは、川口有美子さんの『逝かない身体』です。川口さんがALSのお母さんをどう介護したかはわかったけれど、寝たきりになってしまってからの話がほとんどです。この病気になった人は、診断されてからどう症状が進んでいくのかが知りたいのですが、欲しい情報はほとんどの本にない。だから僕は、自分の状態を毎月定点観察のように書くことにしました」
診断を受けてから二ヶ月後から、最初は「アルジャーノン通信」、今は「ひなたぼっこ通信」として、弁護士活動や福祉活動で出会った友人たちに向けて、症状の進行具合を記録したメールを送り始めた。二百数十人の読み手がいる。
5月30日から車の運転はやめました。突然、右腕の機能低下が進行し、切り返しをするときに右腕が機能しないからです。それ以外はALSがどう進行しているかわかりません。 両腕の力が弱くなってきたので、ズボンを腰から上に通常の位置に持ってくるのが大変で、椅子に座って体をずらしながら通常の位置までズボンを上げるようにしています。 パソコンはなぜか普通に打てますが、右腕は動かないのでマウスを触る時が一苦労です。腕が使えない状態になってやっとわかったことは健常者は腕を使えるからさまざまなことができるわけです。 右腕が全く意思に従わないことで、エレベーターのボタンを押すのも大変ですし、事務所の鍵を回すのも大変ですし、携帯電話で景色を写すのはすごく大変です。なぜならあの軽い携帯電話を左手で持つこともしんどいからです。今の私の進行状態は両腕の機能が大変衰えているというだけです。 電話をしてくれれば分かる通り、普通にしゃべれていると思います。歩くことも普通にできます。ただ感覚的にはいつも太ももの表側の方が30キロマラソンした後のような疲労感を感じています。
自分の状況を知り合いに知らせる意味もあるが、後に続く人に役立てばいいという気持ちからだった。書くことで、病気に冷静に向き合える気もした。
進む症状、増えていくできないこと
症状はゆっくりと進んでいった。
まず、今年4月になると、症状を遅らせるために飲んでいる薬の瓶のふたが開けられなくなった。妻のまゆみさんも開けられないぐらい固いので、札幌に住んでいる長男に、毎月1回、瓶のふたを開けてもらうためだけに来てもらうようになった。
3月中旬には、事務員の一人が辞めることになり、ねぎらい旅行で韓国に事務員3人と行った。滞在中、演劇を見にいった劇場で開演前にトイレに入ったが、終わった後、ジーパンのボタンがとめられない。同行者はみんな女性だし、周りはみんな韓国人だから、助けも求められない。
「結局、ボタンを閉めるのに二十数分かかりました。汗だくになってね。小さい個室の中で、肘を使ったりしてうんうん唸って必死にしめました。旅行に行くからカッコつけたつもりだったんだけど、もうスタイルのいいぴっちりしたズボンは履くのをやめようと思いました。もう力がないんだって気づいてね」
先に引用したように、5月末に運転もやめた。カーブの時にハンドルを回すことがスムーズにできない。6月の誕生日まで運転を続けたいと思っていたが、早めに諦めざるを得なかった。
8月に入ってからは、トイレや風呂を一人で完結できなくなった。
「パンツは上げられるのですが、普通の位置にあげられない。中途半端に上げたパンツを奥さんにあげてもらっています。風呂も自分で入れるし、体も拭けたのですが、パンツを脱ぐことはできても履くことはできない。そのうち上の服も脱げなくなって、背広も自分では手を通すことができなくなりました。今、着ているのは沖縄のかりゆしですが、上の方のボタンがとめられません」
自分で眼鏡を取るのも大変だし、この酷暑で1人で歩いていると汗を拭けずに目に汗が入る。一人で歩くのもしんどくなって、外出する時はなるべくタクシーを使うようになった。この二ヶ月、進行が早まっているのを感じていた。
一度だけ、妻に泣き叫んだ夜
ALSと診断されてから、一度だけ泣いたことがある。
3月頃、何がきっかけだったかは覚えていない。それほど小さなことだ。夜、酒を飲んで少し酔っていた時、症状が進んでできなくなったことを、妻から当然できるかのように言われて、感情が抑えきれなくなった。
「もう今はできないことなのに、その言い方は酷いだろう!俺をもっと理解してくれよ!」
気がつくと泣き叫んでいた。
妻はそんな自分の姿を見て、驚いて黙り込んでいた。
「もう残念だけど、怒っても物も投げつけられない。もちろん物を投げつけたことなんて一度もないですけれど、そんな動作もできなくなった身体です。やれると思ってきたことができなくなっているんだから、配慮してほしいんだと叫んだんじゃないかな」
一番自分の近くにいて、心を許している妻だからこそ、できないことが増えた自分のもどかしさや悔しさをぶつけてしまったのかもしれない。
「それもあったと思いますよ。32歳で結婚して、一緒に生きてきて、どこにコップをしまうとか、どこでテレビのスイッチを切るとか、暮らしのいろいろな場面で暗黙の了解で二人が動いていた。でもその暗黙の了解では動けない状況に、私がなっていっているわけじゃないですか。それにも苛立って、爆発してしまったのだと思います」
妻には後日、声を荒げてしまったことを謝った。
一人で出歩けなくなり、介護の準備も考える
今は自分の足で歩けるが、徐々に一人での外出も難しくなってきた。
二ヶ月前、法律相談があって、電車で札幌から手稲駅で降りた時のことだ。
交通系カードを改札のセンサーに当てようとしたが、腕を上げるのがしんどかった。
相談を終えて、自宅のある小樽駅に帰り、バスに乗った。自宅近くの停留所にまもなく着くタイミングで、降りることを知らせるボタンを押そうとしたが、少し高いところにあって手が届かない。その停留所はほとんど降りる人がいないから、自分が押さないと停まらない可能性が高い。
困ってあちこち探したら、足の近くにもボタンがあることにギリギリで気がついた。バスが通行している最中に立ち上がって、ぶらりと垂れ下げた手で押して降りることができた。
そうやって必死に自宅の玄関にたどり着き、鍵を開けようと思っても、鍵穴のところまで腕が持ち上がらなかった。
「立ってる位置の手は動くから、手の位置にあればできるのだけど、鍵穴の位置にどう手を上げるか。片方でもう片方の腕を押さえて両方の手で開けようとしたり、足場を持ってきて手の位置を上げようとしたり。自分のうちに入るのに、泥棒をやっているみたいでしたよ。それで気がつきました。もうこれは一人では出歩けないのだと」
「今は小樽の自宅と札幌の事務所の往復を、事務員でもあるまゆみさん(妻)に送り迎えしてもらっていますが、一人で出かけることはだんだん難しくなってきたのかなと思います」
9月2日の私のインタビュー中も、何度か額をかく動作をしたが、腕が上がらないため、頭を深く下げて手に頭を近づける形でかいていた。
今は歩くことはできるが、最近は真夜中や明け方に呻き声が出るほど足がつることがある。足も確実に症状が進行しているのを感じている。
一軒家の自宅は、自分の親のために作ったもので、全面的にバリアフリー対応にしていた。車いすを使うようになった時のために、スロープも用意しておかなければいけない。
「いつ頃ヘルパーを頼まなくちゃいけないかなということはもう考えています。今度、小樽市役所に話を聞きにいく予定です。今はまゆみさんがやってくれていますけれども、全てやらせたら鬱になってしまうからね。24時間体制の介護も自治体に申請することになるでしょう」
これからどうやって生きていくのか。車椅子の仲間は、「車椅子になったらこんなことが大変だぞ」と今から心構えを教えてくれている。
「『トイレの介助なんて今でも恥ずかしい。慣れないよ』とか、『そうそう車椅子で入れるトイレがあるわけじゃないから、薬を飲んでおいてトイレに行っておいたほうがいいよ』とか。僕にはそんなことを教えてくれる仲間がたくさんいる。普通の人よりは腹づもりができていると思いますよ」
(続く)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績













