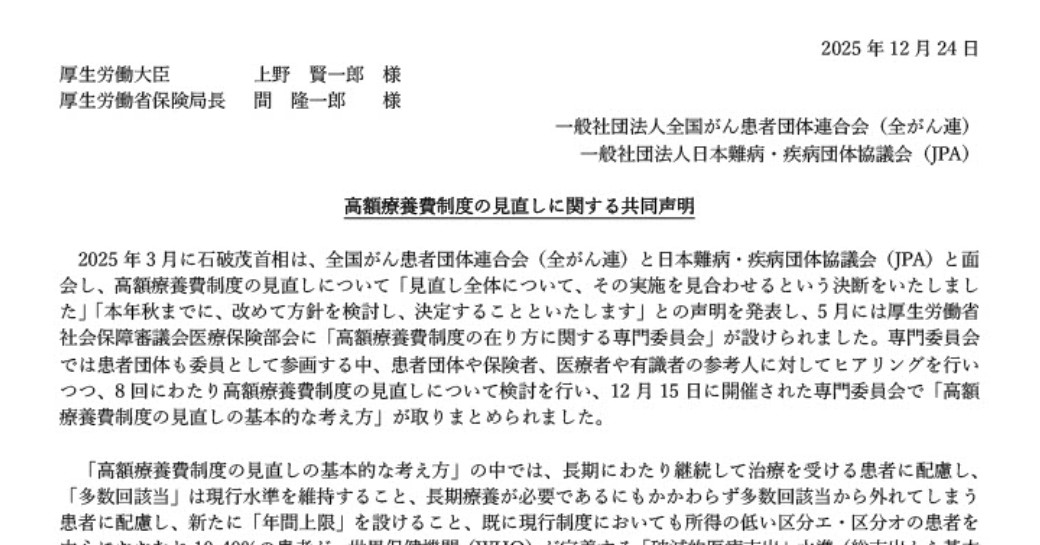グランピングやゴルフでも感染 致死率の高いマダニ感染症、どう防ぐ?
夏にもかかわらず、さまざまな感染症が流行しています。
子供の病気だと思われがちな伝染性紅斑(リンゴ病)も流行しており、妊婦さんは要注意。
致死率の高いマダニ感染症が見つかる地域も広がりを見せていますが、何に気をつけたらいいのでしょうか?
感染症に詳しい医師で薬剤師の峰宗太郎さんに解説してもらいました。

「人間が自然と触れ合う時は、虫が媒介する感染症にも注意が必要」と話す峰宗太郎さん(撮影・岩永直子)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
リンゴ病も流行中 妊婦が感染すると胎児に影響も
——新型コロナ、インフルエンザ、百日咳の他に、どんな感染症が流行っていますか?
リンゴ病も流行っていますね。日本ではお子さんの感染症として有名で、パルボウイルスB19が原因の、ウイルス性の感染症です。
このウイルスは何が怖いかといえば、子供はまず感染してしばらくすると熱が出て、ほっぺたが赤くなって感染してることがわかるのですが、ほっぺたが赤くなる前にすでにウイルスを撒き散らしていて、症状に気付く前に感染が広がるのです。
だから1人患者さんがいたら、周りに広がってる可能性があると思って慎重に対応しなければいけません。
——治療薬はありますか?
全くなく、対症療法になります。怖いのは、お子さんの場合は、熱が出る、顔が腫れるぐらいで済むことが多いのですが、大人が感染すると結構症状がきついことです。関節痛があったり、高熱が出たり、造血の抑制がかかって、貧血気味になったりします。お子さんが感染したら、周りの大人はかなり注意深くみなければなりません。
また、大事なのは妊婦さんの感染予防です。感染すると胎児に影響が出てしまいます。胎児水腫といって、胎児の体にむくみが出たり、流産をしたり、後遺症が残って障害を持って生まれる可能性もあります。
この感染症はワクチンで防げないし治療薬もないので、発症した子がいたら、妊婦さんは近づかない用にする形で防衛をちゃんとしてください。流行中の今は、妊婦さんや妊婦さんのいる家族など身近な方は特に注意してほしい感染症の一つです。
さらにいつも通り、夏に少し流行し始めているのは、手足口病やヘルパンギーナです。これも接触感染や飛沫感染主体なので、引き続き注意をしてほしいです。
様々な感染症が流行ってるので、発熱などの症状から「この感染症だ」と決めつけないことが大事です。熱が出る、皮膚にぼつぼつが出る、咳が出るのは感染症の典型的な症状なので受診のきっかけにはなります。熱中症や「冷房風邪」などと決めつけずに、受診するのは大事だと思います。
虫が媒介する感染症が世界中で流行中
——マダニ感染症も流行っていますね。
実は、今年の1番の話題は「媒介性感染症(ベクター・ボルン・ディジーズ)というものです。ベクターというのは「運び屋」という意味ですが、主に虫だと思ってもらって大丈夫です。有名どころは蚊やダニなどです。
1番有名な媒介性感染症は蚊によって媒介されるマラリアです。マラリアは寄生虫ですが、実は今、寄生虫ではなくベクターで運ばれるウイルス性疾患が世界的には去年から猛威を振るっているんです。ベクターによって運ばれるウイルスをアルボウイルスと呼んでいます。
特に南米で1番流行っていたのは、デング熱、チクングニア熱、ジカ熱、です。そしてウイルスとして前から知られていたのですけれど、大流行となって世界中で死者が昨年どんどん確認されたのが、オロプーシェウイルスです。
この4つが蚊で媒介されて世界中で流行っていて、特にデング熱はブラジルを含む南米で流行っています。去年の死者数はここ数十年で一番多くなっています。
チクングニアウイルス感染症(チクングニア熱)はついに中国に入り込んでしまって、中国で大流行も始まっています。
オロプーシェウイルスもアメリカやヨーロッパで持ち込み例がバンバン出ていて、ブラジルでは死亡例も出ています。ジカ熱に関してもフランスなどヨーロッパでも出ています。
振り返ってみれば、デング熱が2014年に代々木公園で大流行としてからもう10年経っています。ああいうふうに海外からの持ち込みによって、日本の在来種の蚊の中に病原体が入る可能性もあるし、感染した人が来てそこからうつることもあるし、蚊の持ち込みもあり得ます。
気候が温暖化していて、日本は実はもう実質的には亜熱帯なんですよね。そうなると、ベクターである虫の分布が変わってくるので、蚊に媒介される感染症が再び広がる可能性は常に考えなくてはいけません。
実は、戦前・戦時中から戦後早い時期にかけては、沖縄や鹿児島の群島、滋賀県の一部などはマラリアの定着地域でした。蚊が駆除されるなどして、清浄化されたんです。同じく韓国はマラリアの流行国だったのを排除したのですが、今、韓国は再びマラリアの流行が起きています。
蚊のコントロールはベクターコントロールと言いますが、北朝鮮がコントロールできていないんですよ。38度線を越えて入ってくるので、38度線付近でマラリアが去年から結構流行っています。日本より緯度が高いところで寒くてもそうなっているということをよく考えてください。媒介性感染症は引き続き注意が必要ですし、知っていただきたいと思います。
日本で流行中のマダニ感染症
——こうした虫が運ぶ感染症の対策として何ができますか?
虫除けに意識をもう少し払ってほしいです。虫除け剤をちゃんと使う。特にディート(DEET)とイカリジンという二つの成分が基本的によく使われていて、日本のものも優秀なので、怖がらずにちゃんと使うような習慣を身につけてほしいです。
そして、日本では今、マダニ媒介性感染症が流行しています。
マダニは野山の中にしかいないと思われていることもあり、都会の人は危険性を感じないことが多いのですが、野山や畑、公園などだけではなく、散歩に連れていった犬にも、奈良などの鹿にもくっついている。猫も外から持ってきたり、あとは渡り鳥にいっぱいついていたりして、そこから入ってきます。
いわゆるダニ類を介した感染症で有名なものは色々あるのですが、日本でやはり話題なのは、「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」という致死率の高い病気を起こす、マダニ感染症です。
それ以外にもマダニを介した感染症は日本はじめ世界中でたくさん新しく見つかっています。よく知られている者としてはドイツ、フランス、ロシアと北海道をつなぐベルトにある、渡り鳥が運んでくるダニ媒介性脳炎(TBE)というものもあります。
ドイツやフランスの農村部などに住んでいる人は警戒をしていて、いいワクチンもあります。だけど、日本人はほとんど打っていないから、もし、ドイツなどに行かれる方がいたらうってほしい。北海道でも去年報告が出ています。日本にも入ってきているということを考えてほしいですね。
——感染したら、どうやって気づくのでしょうね?
ダニに噛まれたら必ず注意が必要で、発熱をはじめとする症状がでたら受診し、検査で確定診断という状況です。
——マダニに噛まれた後にどうにかしたら感染は防げるのですか?
噛まれた後にはどうにもなりません。SFTSについては効果的な治療薬はない(アビガンは使うことができる)のですが、早く対処できれば集中管理をするなど対症療法・支持療法ができます。
マダニは一度噛んだら、長いと1週間ぐらいくっついています。噛まれたら絶対に油断せずに、病院にかかっておく方がいいです。噛まれた時点で発症していなくても、皮膚科などに行ってダニを取ってもらったほうがいい。
媒介されたウイルスの感染はすぐに成立してしまいますが、受診しておけば発症時に役に立つヒントはたくさん残せるし、その医療機関がダニを取っておいてくれれば、後で検査もできます。
それ以外にも、エゾウイルスというウイルスを北海道の研究者たちが見つけていて、これもダニ媒介の感染症です。しかも死亡例も出ています。
あと最近では、オズウイルス感染症です。これも日本で1例だけ症例が出ています。
SFTSは、とても怖いタイプのウイルス感染症です。マダニから感染するのですが、中国、韓国でも見つかるし、日本では西日本、特に豊後水道のあたりに多く分布しています。宮崎県とか岡山、広島、四国の北側に多いです。
野生動物を調べると、イノシシでも鹿でも抗体保有率が高いし、マダニを集めてきてすりつぶして検査をすると、いっぱいウイルスが出てくる。
SFTSについてはマダニに刺されるのが1番の感染ルートなのですが、病気になった猫に噛まれるのも原因になるし、実は、ヒトーヒト感染もあって、重症のSFTS患者の処置をしていたお医者さんが感染したであろうという事例が既に日本でも報告されました。韓国でも報告されています。
このウイルスは、致死率が高齢者になるほど高くなるんです。メカニズム・理由はまだわかりません。50歳以上の人で発症率もより高いし、死亡率も年齢とともに上がります。全年齢で死亡率は30%ぐらいですが、60代、70代以上で見ると8割近くがよくない予後となります。
マダニ感染症、治療法は?
——SFTSに特化した治療法はないのですね。
全身管理をして、徹底的に呼吸を支える、循環を支える輸液をする、炎症を抑える、熱を下げることをしないと、簡単に致命的になります。一応、アビガン(ファビピラビル)は、日本では特別な承認で保険で使えるようになりました。
しかし、診断にも時間がかかるので、SFTSだとわかった時には治療開始が遅い状況ということもあります。確実な期待はできませんが、集中治療すれば助かる例もあるので、とにかく発症したと気づいたら受診してほしい。
予防は基本、野山に入る時は長袖、長ズボンを着用し、先に話した虫除けを使いましょう。
動物にくっついて入ってくるので、ペットもちゃんとチェックしてあげてほしいです。特に外で飼ってる犬や外にも出歩く猫は危ない。猫では症状が強く出ることが分かっているので、病気の猫がいたらとにかく近づかず、噛まれないようにすることも大事です。獣医さんも十分注意してほしいですね。
SFTSは西日本に多かったのですが、今はどんどん広がってきて、静岡、神奈川、北海道にも今年は症例が出ています。全国に広がってきているという意味でも、注意をしてほしい感染症です。
動物界にいて、虫の媒介で入ってくるウイルスなどの感染症を起こす病原体はパンデミックのような急激な大流行にはなりません。
でも、静かにそういうところに触れ合う人の命を奪っていき、推計だけでもう1000人近くが感染し、100人以上が亡くなっています。十分注意が必要です。
他にもキツネから来る寄生虫であるエキノコックスの分布は北海道だけとみんな思っていますが、2005年には埼玉の犬でも確認され、分布が広がっていると思われます。ダニ媒介性脳炎のウイルスもも北海道の外の野生動物からも検出されています。
自然と人間の触れ合いは、田舎の都市化が進んだからだ、などと言われていましたが、最近は温暖化の影響や、動物が人間の住む方へ入ってくることもあります。
触れ合うと、新しいウイルスが広がるのは太古の昔からあることです。古いのは、飼い慣らしたラクダなどから天然痘が発生したと考えられることなどもそうでしょう。サルからやってきたHIVや、コウモリからやってくるエボラウイルス、齧歯類からのエムポックスなどもあります。
グランピングやゴルフでも感染
人獣共通感染症がやってきて、人の中で慣れる、馴化すると流行がヒト—ヒト間で回り出す可能性が出てきます。怖いです。
自然と接すると、熊のように直接襲われることだけではなく、病気がやってくる可能性もあることを常に考えてほしいです。
——日本だとどういうルートで人にうつってくるのですかね?
猟師さんや山菜取りの人など野山で働くような人が多くて、もう1つは郊外のおうちで野山や田畑が近いところで犬の散歩など日常的にマダニに刺されやすい行動範囲で生活をしている例などですね。
マダニに刺される症例で言えば、最近は、グランピングやキャンピングなどもなんですよ。グランピングの施設がオープンした近くでマダニ感染症の患者が発生したりしています。キャンプ、グランピング、意外にゴルフもありますす。自然と触れ合う活動やスポーツのときにはマダニにも気をつけたほうがいいですね。
(続く)
【峰宗太郎(みね・そうたろう)】医師、薬剤師
京都大学薬学部、名古屋大学医学部を卒業し、薬剤師免許、医師免許取得。国立国際医療研究センター、国立感染症研究所、東京大学大学院医学系研究科(博士(医学))、NIH(アメリカ国立衛生研究所)博士研究員、帰国後は、国立感染症研究所や厚生労働省での勤務を経て、現在はフリーランス。病理専門医(血液腫瘍・感染症)、専門はウイルス/ワクチン研究。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績