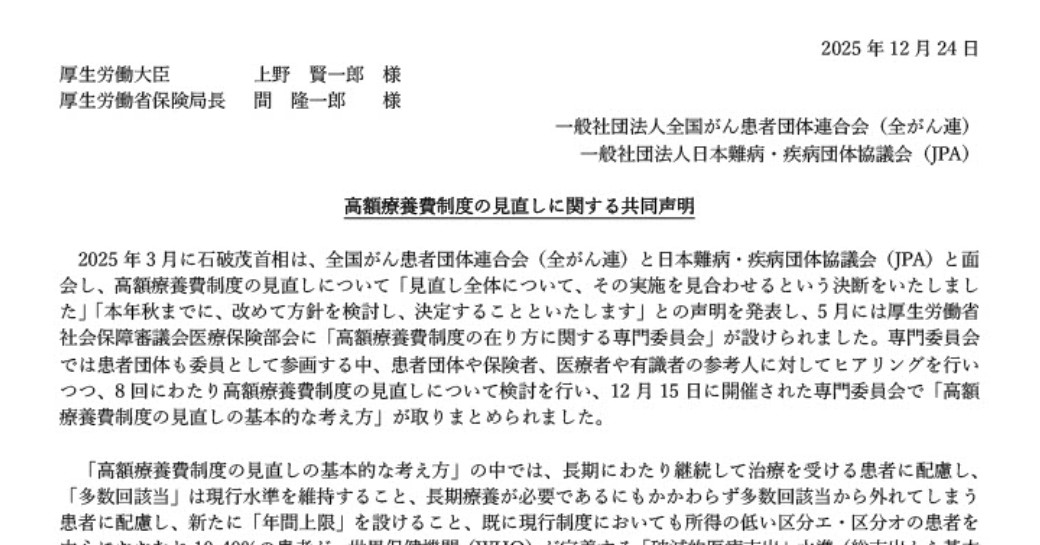食中毒は増加、性感染症も流行中 新しいワクチンに期待できること
この夏、さまざまな感染症が発生・流行しています。やはり気をつけたいのは食中毒。性感染症も相変わらず増えています。
何に気をつけたらいいのでしょうか?
感染症に詳しい医師で薬剤師の峰宗太郎さんに解説してもらいました。

峰宗太郎さん(撮影・岩永直子)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
鶏肉の生食は危険 カンピロバクターからギランバレー症候群になる可能性も
——夏は食中毒も心配ですね。
SNSでも話題になっていますが、「加熱すれば菌が全部死ぬ」というのは幻想です。ウェルシュ菌やセレウス菌は加熱をしても生き残っていたり、芽胞菌という強い菌も残っていたりするわけです。
まずは、それぞれの菌の特性を知ることが必要です。
「チャーハン症候群」が少し話題になっていましたが、セレウス菌は、朝にチャーハンを作ったら加熱してあったとしても、生き残って夕方ぐらいまでに増えてしまうので、夕方に食べてお腹が痛くなることや熱が出ることもあります。
ウェルシュ菌はカレーが有名ですね。辛子蓮根などについては風評被害もあるのですが、真空パックにするような食材は酸素が遮断されてボツリヌス菌が生き残って増殖することもあるから、注意はしてほしいですね。
だから加熱していても油断をしないことは大事なのですが、同時に加熱の重要性も改めて強調したいです。
この前、宮崎県でもそのカンピロバクター腸炎の集団発生がありました。日本中どこでも発生しています。
カンピロバクター・ジェジュニとカンピロバクター・コリが主な原因菌ですが、原因食材は圧倒的に鶏肉が多いです。
加熱が不十分な鶏肉を直接食べることだけではなく、火の通っていない鶏肉を調理した器具や手を介して感染することもありますし……伝統食として、鳥刺しを提供することなどがあって、そこから感染する場合もあります。自治体は色んな基準を独自に作ったりしていますが、加熱以外に確実に防ぐ方法は全くありません。独自基準なんてまず無意味です。
ギラン・バレー症候群が感染から発症することがあります。高知県からの昨年の報告も踏まえて言うと、カンピロバクター腸炎を起こしたときに、そのカンピロバクターに対する免疫(抗体)ができることがあるわけです。それはガングリオシドという人間の神経の周りを守っている「鞘」の成分と形がにているために、免疫の効果が交差するんです。
つまり、交差免疫というのができて、菌を攻撃するためにできた抗体が、自分の神経まわりを攻撃し始める。そして、神経が麻痺する疾患であるギラン・バレー症候群を起こします。筋力低下や麻痺を起こし、悪化すると呼吸筋を侵して死に至ることもあります。
汚染された生の鶏肉(鳥刺しなど)→カンピロバクター腸炎→ギラン・バレー症候群という関係は、今ではかなり明確になっています。西日本の鶏の生食地域ではギランバレーが多いのではと調査もされています。
ギラン・バレー症候群は、軽症であれば歩きにくさ、動きにくさが出るだけのこともあります。しかし、呼吸筋まで麻痺すると死ぬこともあります。人工呼吸器でしのいで、ゆっくり回復してくる例が多いんですが、長引く人、後遺症の残る人、亡くなる人もいるので、注意が必要です。
調理器具は熱湯かハイターで殺菌を
——そうなると、鶏は生で食べるな、というわけですか。
強く言えばそうなのですが、これを言うと一部の地域の方はものすごい反発をします。何しろ厚生労働省が、「生の鶏を食べるなキャンペーン」をやろうとしたら、強い抗議があって、ある地域の医師会や保健関係者も強く言えなくなったようなこともあります。
——鶏肉は、周りをカットしても無駄なんですよね。
全然ダメです。火を通すしかありません。
——豚肉と一緒ですね。
豚もダメですね。豚は、飼育されているものであれば主にウイルス性疾患であるE型肝炎などを恐れるのですけれども、言うほど発生しないんです。実際にはたまの事故ぐらいです。
——家庭で鶏肉を調理する時に気をつけたほうがいいことはなんですか?
まず鶏肉は水で洗ってはいけません。水道水で洗うと飛び散って、そこら中、菌だらけになります。だからすぐ火や調理するお湯に入れる。カットで使ったまな板などは、熱湯をかけて消毒をするか、ハイターのような塩素系の漂白剤をしっかり使う。この2つしかないですね。
——家ではハイターを包丁とまな板、調理器具に使っています。
ハイターは適切な濃度ならだいたい何の病原体にでも効きますよ。ウイルスを扱う研究所でも、この成分を含む液体に器具などを漬けることは多くあります。
食中毒も、この夏も、増えてますから、とても注意をしてほしい感染症の一つです。
性感染症も増加傾向が続く
もう一つ、この夏、かなり増えていて厄介なのは性感染症です。
——梅毒ですか?
梅毒は確かにとても多い。ここ数年ずっと猛威を振るっています。梅毒、クラミジア、淋菌。特に淋菌、クラミジアは耐性菌が増えていて、これまで普通に使えていた抗菌剤でなかなか治らないものも増えているし、多重感染すると厄介です。
性感染症の増加は色々理由があるのですが、一つにはインバウンドはじめ海外との交流で増えた可能性があるのではないかと言われています。細菌の遺伝子解析などの明確な証拠は十分にはありませんが、中国南部で流行っていた系統の菌による梅毒が流行っていたことはあるようなので、それはあるのかもしれません。
もう1つは、若い女性から主婦層などに感染者が多いので、おそらく「パパ活」や不倫、こっそり風俗バイトをしている人など、性交渉によるつながり(ネットワーク)が思っていたより多いということはあるようです。
発表やデータに出てくる部分ではありませんし、接触者調査のデータはなかなかないのですが、疫学の調査でも調査の内容にそういった状況がでてくることはあるようです。
だから、性的アクティビティの高い人は、誰でも、性病にかかる可能性があると思って対応してほしいのが特にこの3つを含む性感染症です。
——どんな症状があったら、性感染症を疑うべきですか?
特に陰部のできものや痛み・不快感、尿道が痛む、排尿痛がある、皮膚に皮疹が出てくる、喉が痛いわけのわからない熱が出ることがあって、なおかつ、その前に性的な接触があれば可能性はありますので、恥ずかしがったり過剰に怖がったり、無理をしたりせずに受診してほしいですね。
特に女性の場合は早く治療を開始したほうがいいことが多い。不妊につながるものもあるからです。だからこれはもうぜひ知っておいてほしい。慢性的な炎症になっている例も結構あります。
ここのところ僕も性病については4人ぐらい診断しましたからね。そういうお店に行って、1週間後に皮膚がこんなふうになったということで検査して梅毒がみつかったというような形で。
まずは怖がらずに受診して検査を受けてほしいし、その場合は、HIVも検査してほしいところです。日本ではHIVの感染率はそんな高くないのですが、念のため、でも大事です。いまだに「突然エイズ」(エイズを発症してHIV感染に気づく例)の人もいます。
性感染症対策を
——治療をすれば基本的には治るわけですね。
特に梅毒は比較的簡単に治ります。早めに診断さえすれば。
逆に診断しないと将来的には死につながってしまう可能性もあるし、進行すると精神的な異常をきたす可能性もあります。なにより他の人にもまたうつす可能性がありますしね。
クラミジアや淋菌は最近、薬への耐性によって難治性のものが増えているし、クラミジアは放っておくと特に女性不妊つながることがあるので、しっかり対応したほうがいいです。
また子宮頸がんなどの複数のがんを防ぐHPVワクチンは引き続き受けたほうが良いです。
自治体によっては男性への補助も始まっているので、男女ともに、ぜひ接種を考えてほしいです。男性に関するアップデート情報としては、海外では男性に多い中咽頭がんを防ぐ効果を証明する論文が次々に出始めています。
男性の中咽頭がんは、女性の子宮頸がんと同じく、HPVの16型、 18型で起きるものがほとんどで、アメリカではHPV由来のがんの症例数は子宮頸がんよりも中咽頭がんのほうが多い可能性もわかってきています。
つまり、男性の方がHPVによって命を落としていたのではないかという説さえもあって、男性を守るという意味でもかなり重要なワクチンなのです。
それに、以前から僕もHPVワクチン関連のインタビューのためにチラッと言っていましたが、子宮頸がん、中咽頭がん、肛門がん、陰茎がん、外陰がんを防ぐのに加え、一部の皮膚がんを防ぐ可能性も言われはじめています。
新しい研究では、皮膚がんの一部はやはりHPVが関与していそうだと言われています。若ければ若いほど効果を発揮しますが、まだ受けていない成人に対しても、接種することをつよく推奨するワクチンですね。
RSウイルスワクチンが実用化、マラリアワクチンも開発中
ワクチンの開発は世界的にすごく進んでいます。最近、話題のワクチンは、RSウイルスのワクチンです。これは日本でも承認されたし、アメリカでは65歳以上のRSウイルスによる呼吸器疾患による死亡をかなり防いでいることがわかってきました。ぜひRSワクチンは接種を考えてほしい。
最近、淋菌のワクチンもいい成績を出し始めているようですし、マラリアのワクチンも、ようやくいろんなタイプのものが出てきて、効果が期待できるものが普及するのは時間の問題かもしれません。
——逆にマラリアのワクチンってなかったのですね。
世界の三大感染症は、マラリア、結核、HIVです。
この3つの感染症の特徴の1つは、ワクチンを作るのがとても困難だということです。今まで有効な方法はない。逆にどれも治療法はあるんです。
——あれ?結核はBCGがありますよね?
BCGは結核の感染・発症自体大して防ぎませんからね。子どもの結核性髄膜炎を抑制する効果はあるぐらいのものですかね。僕はひろくうった方がいいとは思っていますが、全ての結核を防ぐかといえば、全く防がないよねっていう感じです。世界3大感染症は、治療薬はどれもかなりしっかりとある。予防法もかなりわかっているのですが、ワクチンはなかなかいいものがありませんでした。
——アフリカなどに行く時、トラベルクリニックでマラリアのワクチンをうってから行くものなんだと思い込んでいました。ワクチンはなかったのですね。
マラリアは今でも予防薬をあらかじめ飲み始めて、持っていくのです。抗マラリア薬のマラロン(アトバコン・プログアニル塩酸塩)などを飲みながら、蚊帳と虫除けを持っていく。
予防内服をしていれば、マラリアの寄生虫が体に入ってきてもすぐ退治できることが期待できます。僕も去年は、コンゴ民主共和国に複数回行きましたが、毎回マラロンなど飲んでいました。
アフリカなどの流行地に行く時に必須になることが多いのは、マラリアの予防薬を飲むことと、黄熱のワクチンをうつことです。それをうっていないと入れない国があるんですね。黄熱もアルボウイルスです。それ以外にも外国は地域ごとに接種しておくことが勧められるワクチンがいろいろありますね。
優秀な帯状疱疹ワクチン
もう一つ、最近のワクチンの話題として、帯状疱疹ワクチンは優秀です。
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスというヘルペスウイルスの一種が原因です。子供の頃に感染して、一生体の中にいます。免疫の状態が悪くなった時に再活性化して、そのウイルスが潜んでいる神経節に沿ったところの皮膚に帯状に皮疹が出るのが典型的な症状です。
ウイルスが再活性化している時もすごく痛みが出ますが、問題は、ウイルスがまた静まった後にも「帯状疱疹後神経痛」という大変な神経痛が残ることがあることです。そうなると、残りの人生、30年、40年、毎日痛くなるようなこともあり、とても嫌なものです。
また、顔の神経から出ると失明する人もいるし、顔面神経にも波及してしまうと顔に神経麻痺が残る人もいます。耳が聞こえなくなる人などもいるので、決してなめていい病気ではありません。
水痘・帯状疱疹ウイルスは空気感染もするので、子どもの多いところで水ぼうそうの人がいると、わーっと周りに広がるんですよ。ですから過去に感染している成人は、水ぼうそうの子供と触れ合うと、ウイルスに曝露するので、「ブースター効果」が出てくることがあります。
だから昔は帯状疱疹をあまり発症しないおじさん、おばさんが多かったわけです。子や孫などの水ぼうそうで免疫が「ブースター」されるからです。
ところが、最近は子供がみんなワクチンをうつようになったので、水ぼうそうにそもそもなりません。そうすると、逆に高齢者とか大人の世代はブースターがなされないので、帯状疱疹の発症率は静かに上がってきているんです。
また、高齢者が増え、免疫状態が下がる人も増えているので、やはり増える。
そしてもう1つ、意外なことにがんになると帯状疱疹が出ることがあるんですね。やはりがんは免疫にすごくダメージを受けますから。逆に帯状疱疹をきっかけにがんがわかることもあるので、そういう意味でも怖い病気です。
しかし、この場合はワクチンがとても優秀です。特に、シングリックスというワクチンは販売が開始されてから5年ぐらいぐらいしかまだ追跡はできていないのですが、この5年間で接種者における発症率はかなり下がってるし、時間が経っても効果は大きくは落ちていないし、とてもいいことが明らかになっています。
なぜか認知症も防ぐ効果も?
このワクチン、帯状疱疹自体を防ぐのにもとてもいいのですが、最近、それに加えて、メカニズムは全く不明ながら、帯状疱疹ワクチンをうった群はうっていない群と比べて、認知症・認知障害の発生が抑えられることがわかってきています。
特にMCIと呼ばれる軽い状態の認知症の発症がとても抑えられていることがわかってきています。
これは、理由はよくわかっていなくて、実はインフルエンザワクチンも多数回接種している人ほど、認知症の発生率が下がっているのではないかという話は昔からあります。何かウイルスや感染が悪さをしているのかもしれません。
逆に、悪い影響については、従来通り、基本的な副反応以外は長期の観察でも出ていないので、50歳以上で、ぜひうってほしいワクチンです。公的補助があるのであれば活用してほしいですね。
色々な感染症に対するワクチンは、一見、自己負担もかかるから高いと思う人もいますけれど、入院したり、ICUに入ったりすると1日で100万円以上の治療費がかかるようなこともあります。帯状疱疹の痛みなどは、発症後に取り返しがつかなくなって付き合い続けなければならなくなり後悔している人ばかりなので、ワクチン接種をぜひ考えてほしいですね。
(終わり)
【峰宗太郎(みね・そうたろう)】医師、薬剤師
京都大学薬学部、名古屋大学医学部を卒業し、薬剤師免許、医師免許取得。国立国際医療研究センター、国立感染症研究所、東京大学大学院医学系研究科(博士(医学))、NIH(アメリカ国立衛生研究所)博士研究員、帰国後は、国立感染症研究所や厚生労働省での勤務を経て、現在はフリーランス。病理専門医(血液腫瘍・感染症)、専門はウイルス/ワクチン研究。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績