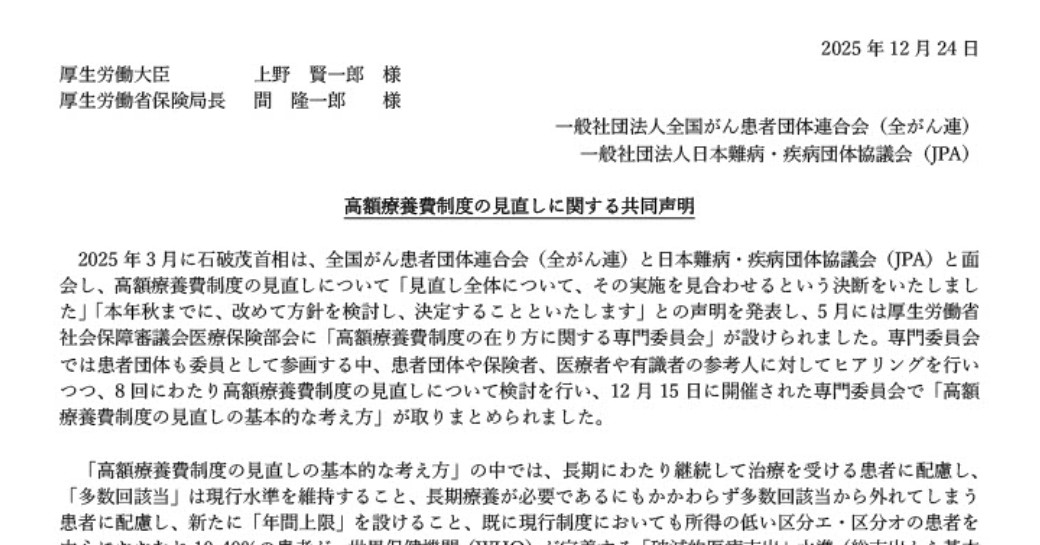咽頭結膜熱(プール熱)、溶連菌感染症、なぜこんなに国内で流行しているの?注意すべきポイントは?
この冬、季節性インフルエンザに続き、咽頭結膜熱(プール熱)や溶連菌感染症が猛威を振るっています。
なぜこんなに流行しているのでしょう?一般の人、そして専門家が気をつけるべきポイントは?
感染症の専門家で小児科医でもある川崎市健康安全研究所所長、岡部信彦さんに聞きました。

岡部信彦さん(撮影:岩永直子)
※インタビューは12月12日に行い、その時点の情報に基づいている。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
インフルエンザ、咽頭結膜熱、溶連菌感染症が増加 なぜ?
——季節性インフルエンザや咽頭結膜熱(プール熱)、溶連菌感染症が国内でいつになく流行しています。なぜなのでしょう?

感染症週報2023年第47週(第47号)より/国立感染症研究所
まず、咽頭結膜熱ですが、プールで広がることをきっかけに見つかった病気なので「プール熱」という病名で知られています。しかし、プールだけで広がる特殊なものではなく、多くの感染症のように普通の生活の中から広がることが多い病気です。
もともとは夏の感染症の一つとされていましたが、最近では夏の流行がひとまず落ち着いた後に、秋から初冬にかけて再び増加するというパターンになってきています。プールだけでうつるわけではない一方で、プールは夏だけのものではなくなっているのも一つの原因となっているかもしれません。
現在の流行状況は、この感染症の調査が始まって以来、突出したものとなっています。明確な理由は、わかりません。
2020~2022年はほとんど流行しなかったのは、新型コロナウイルス感染症の流行で、今まで手を洗わなかった人も洗うようになり、マスクもするようになったからかもしれません。ソーシャルデイスタンスもとられていました。
それで感染が抑えられていたのが対策緩和で戻った、という見方もできるかもしれません。また3年間流行がなかったので、かかった人が少なくなり、免疫を持つ人が少なくなったので一気に広がった、というのも大きな理由になるだろうと思います。
しかし、そうであれば、すべての感染症が増えてもいいわけですが、ほとんど増えない感染症も結構ある。コロナの影響だけでは説明がつきません。
それに日本では手洗いもマスクも熱心に行う人が多かったのですが、海外では必ずしもそうではなかったのに、やはり感染症全般が激減しました。そして、感染症は全てコロナに置き換わったかのようになりました。
最近の感染症の流行は、コロナ対策が緩和された結果、人の動きが戻った影響はやはりあるのでしょう。その状況下で、増えやすい感染症とそうでない感染症があるのかもしれません。
ただ、「手足口病」と「ヘルパンギーナ」は両方とも似たようなエンテロウイルスが原因となりますが、この夏、ヘルパンギーナは記録的な増え方をしたのに、手足口病はそんなに増加していません。
また、突発性発疹はこの数年間低めながらも一定数発生していたのに、今年は今までで最低の発生状況となっています。これもよくわからないところです。
咽頭結膜熱ってどんな病気?
——咽頭結膜熱、溶連菌感染症ってどんな病気なのでしょう?
咽頭結膜熱は、
-
咽頭(喉)が赤くなり
-
結膜(いわゆる「白眼」)が赤くなり
-
かなり高い熱が出る
感染症です。
この病気は、確かにプールで感染が広がって病気が見つかったという歴史的経緯があって「プール熱」と呼ばれるようになりました。そしてその原因は「アデノウイルス」というウイルスの感染であることが後になってわかりました。
アデノウイルスはいくつかのグループに分けられ、高熱を出すもの、肺炎を起こすもの、結膜炎をおこすもの、膀胱炎を起こすもの、胃腸炎をおこすものなど多彩です。がんになる性質を持ったアデノウイルスもあります。
その中に、咽頭結膜熱の原因となるいくつかのアデノウイルスがあります。本来は前述した3つの症状が揃ったものが「咽頭結膜熱」という病名となります。でも、そのうち2つの症状があり、アデノウイルスが検査で陽性になったりすると「咽頭結膜熱ですね」と説明されたり、届け出されたりすることもあります。
また、3つの症状が揃って「咽頭結膜熱=アデノウイルス」と思って検査をしていると、エンテロウイルスなど他のウイルスであったりすることもあり、単純に判断できないことがしばしばあります。
そうなると、咽頭結膜熱という病気を診ているのか、アデノウイルスというウイルスを診ているのかわからなくなります。
今増えているのは「咽頭結膜熱」という3つの症状が揃った病気かもしれないし、咽頭結膜熱の3つの症状はそろっていないけれどアデノウイルス感染を診ているのかもしれない。おそらく、報告はそれらが混在しているのではないかと思います。
幸い、今の「咽頭結膜熱」の流行の中では、肺炎を起こしやすいアデノウイルスや、目の出血を起こしやすいアデノウイルスは増えていないようです。
——感染経路は?
のどが赤くなる呼吸器感染なので、飛沫感染が中心となります。またアデノウイルスは便にも潜むので、ノロウイルスのような接触感染もあります。
プールでの感染はプールの水を介した感染です。ただし、水質の管理が行き届いているプールでは、咽頭結膜熱などのウイルス感染はほとんど生じません。
プール熱、治療法や予防法は?
——治療法は?
抗インフルエンザ薬のようなアデノウイルスに対する治療薬はなく、基本的に対症療法になります。
——予防法は?
一部の国ではワクチンが使われていますが、日本では使用されていません。呼吸器感染症、接触感染の注意として、マスクをする、手洗いをする、うがいをするなどの、基本的な感染症対策が大切です。アデノウイルスやヘルパンギーナや手足口病の原因となるエンテロウイルスは、症状が回復しても1~2週間、長いと4週間くらい便からウイルスが見つかります
ですから、本当に感染を遮断するのだったら、かかった人は1か月間外へ出ない、人と接触しない、ということが必要になりますが、それは実際には不可能なので行われません。
しかし小さい子供の排せつ物の取り扱いの注意や、少し大きい子供に関しては日常的に排便の後にはきちんと手を洗う習慣を身に付けさせておくこと、プールの前にはシャワーなどでちゃんと体をきれいにしてから入ること、などが重要となります。
——亡くなったりはしないのですよね?
咽頭結膜熱で亡くなる人は滅多にいません。稀に起きることを言えば、アデノウイルス感染症で脳炎を起こしたり、特殊な肺炎を起こすことはあります。でも一般的には亡くなるほどの怖い病気ではないです。
アデノウイルス感染は、僕ら小児科医もヒヤッとするぐらい高熱が続くので、他の病気と見分けることが重要になります。高熱が続く時に検査をして、アデノウイルスと分かれば少しホッとするような感じです。
溶連菌感染症ってどんな病気?流行すると「人喰いバクテリア」も増加
——溶連菌感染症はどんな病気でしょう?なぜ今、流行しているのでしょうね。
溶連菌とは「溶血性連鎖球菌」の略称で、流行する溶連菌感染症はそのほとんどがA群溶血性です。連鎖球菌と言われる菌です。熱や喉の痛み、全身に出る赤いぱらぱらとした発疹や舌にイチゴのようなぶつぶつとしたものができるのが特徴です。
また溶連菌感染症は「二度なし病」ではなく、何回も繰り返すことがある感染症です
これが今なぜ流行しているのかも、正しい答えを持っていません。
細菌性感染症なので、抗菌薬(抗生物質)、特にペニシリン系の薬が有効です。ただ、現在は抗菌薬が全国的に不足しているので、無駄なく必要な人に十分行きわたるようにしなくてはいけません。困った現象です。
早めに抗菌薬を飲めば、1~2日以内で他の人にはうつさなくなります。
しかし、喉の奥などには菌が残っている状態が続くので、これをしっかり治療せずに中途半端にしてしまうと、急性腎炎やリウマチ熱などの合併症を引き起こすことがあります。
腎炎は血尿が出てきます。リウマチ熱は関節痛や胸の痛み、手足がまるで踊っているかのように勝手に動き出す運動(不随意運動)などを起こすことがあり、心臓の弁の異常などに注意が必要です。
だから小児科医は子供が溶連菌に感染すると「おしっこと心臓をよく診ろ」と指導されます。
溶連菌はそのような重い病気のきっかけにもなるので、抗菌薬を指示された日数、きちんと飲み切って治すことが必要です。「熱が下がったからもう薬はいらない」ではなく、1週間から10日間、医師の指示通り抗菌薬を使って菌を完全に除去しなければなりません。
それでも再発はあり得るのですが、途中で飲むのをやめて再発、よりはずっと少なくなります。
溶連菌の治療がきちんとできるようになって、小児科の中でリウマチ熱や腎炎を診ることは本当に少なくなりました。こじらせると慢性の腎炎になったり腎不全になったり、大変なことになるので、きちんと治すことが大事です。
もう一つ、溶連菌で怖いのは、「劇症型溶連菌感染症」に進行してしまうことです。いわゆる「人喰いバクテリア」と言われる危険な感染症ですが、稀にこの劇症溶連菌感染症を引き起こしてしまうことがあります。
溶連菌が流行するにすれて、劇症型も少しずつ増えてきています。
劇症型も抗菌薬が効くのですが、厄介なのは菌が増えるスピードの方が、治療の効果が出るスピードよりも早いことです。
劇症型は、筋肉の壊死を起こしてしまうので、菌が身体中に広がるのを防ぐために感染した部分を切断せざるを得なくなってしまいます。それでも急速に進行して、多臓器不全を起こし、死に至ることも稀ではありません。
いずれにしても溶連菌感染症であることが明らかになった場合には、たとえ軽いように見えてもきちんと治すことが必要です。
食中毒の原因にも
溶連菌は、稀ですが食中毒の原因にもなります。
例えば、溶連菌に感染した影響でオデキができていて、その手で作ったお弁当を食べたり、咽頭炎にかかっている人がマスクもつけずにくしゃみをしながら調理をしたものを食べたりなどすると、それを食べた人が溶連菌にかかって食中毒を起こすことがあります。
他の細菌性食中毒と違って嘔吐や下痢などの症状は少なく、食中毒として分かりにくいことがあります。同じ食品を食べた人の中でお腹を壊して、熱やのどの痛みを訴える人が複数いるような時は、食中毒を疑ってきちんと診断と治療を受ける必要があります。
溶連菌の感染経路、予防法は?
——溶連菌の感染経路は?
基本は呼吸器感染なので飛沫感染です。つばや手のオデキ、とびひからの接触感染もあります。
——簡単に感染するのに、油断していると大変なことになるなんて意外と怖い病気ですね。
そうです。意外と怖い。でも抗菌薬で治療ができるので、熱と喉の痛みとか、発疹や舌のぶつぶつが出たら医師の診察を受けてください。溶連菌感染症であれば、指示通りにきちんと薬を飲み切ってほしいです。
同時流行の可能性は?親にもうつる?
——インフルエンザも多いですし、新型コロナも徐々に増え始めています。咽頭結膜熱(プール熱)や溶連菌とそうした病気が同時流行を起こしたら、大変なことになりそうです。
「同時流行」は同時に出てくるのか、追いかけるように出てくるのかによって、大変さが違ってきます。複数の感染症が同時に大流行ということは経験的には少ないです。異なる感染症の流行は少しずつずれることが多いです。
小児科は冬になると感染症で忙しくなるのはいつものことですから、想定の範囲であるかもしれません。
——これらの病気は親にもうつるわけですね。
大人もうつります。アデノウイルスの免疫がなければかかりますし、溶連菌は子供がかかることが多いのですが、劇症型や食中毒は大人でも見られます。誰にうつるかわからないのでしっかり治すべきなのが溶連菌です。
アデノウイルスは目下のところ良い予防法がありませんが、新型コロナと同じく、感染症の基本的な対策を身に付けておくことが重要です。
(続く)
【岡部信彦(おかべ・のぶひこ)】川崎市健康安全研究所所長
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大小児科助手などを経て、1978〜80年、米国テネシー州バンダービルト大学小児科感染症研究室研究員。帰国後、国立小児病院感染科、神奈川県衛生看護専門学校付属病院小児科部長として勤務後、1991〜95年にWHO(世界保健機関)西太平洋地域事務局伝染性疾患予防対策課長を務める。1995年、慈恵医大小児科助教授、97年に国立感染症研究所感染症情報センター室長、2000年、同研究所感染症情報センター長を経て、2012年、現職(当時は川崎市衛生研究所長)。
WHOでは、予防接種の安全性に関する国際諮問委員会(GACVS)委員などを歴任し、 西太平洋地域事務局ポリオ根絶認証委員会議長、世界ポリオ根絶認証委員会委員などを務める。日本ワクチン学会・日本小児科学会・日本小児感染症学会・日本感染症学会名誉会員、アジア小児感染症学会会長(現在理事)など。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績