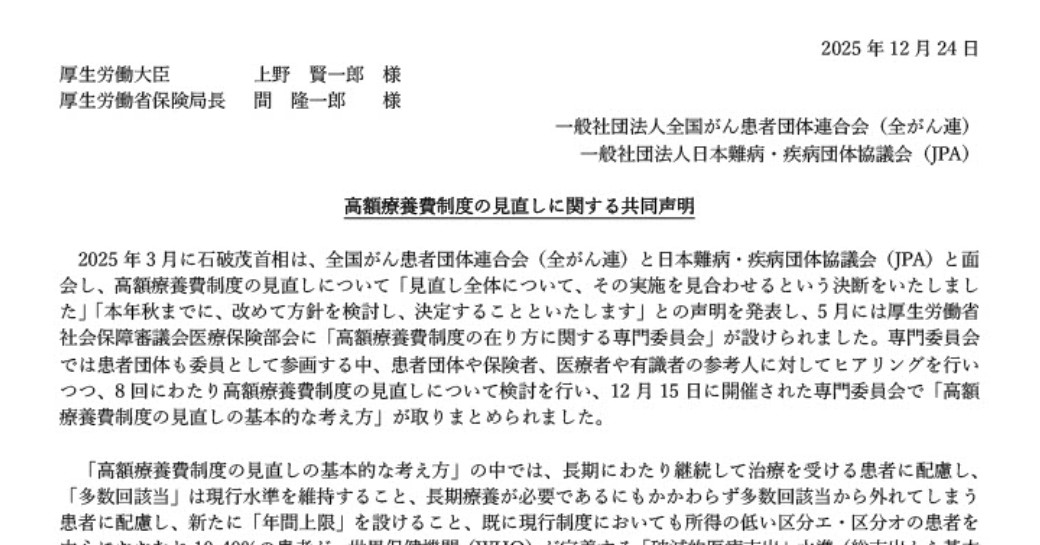健康でない私たちを居心地悪くさせているのは何? 弁護士と新聞記者が語り合った、慢性疾患を生きる人のリアル
一見、「健常者」だが、頭痛やだるさ、めまいなどがあるのは当たり前。命に別状はないけれど、学業や仕事、家庭生活などあらゆる場面で、「ちゃんと」振る舞えてこなかった——。
そんな共通の悩みを抱えた弁護士と新聞記者の二人が、ウェブでの往復書簡による連載をまとめた著書『あしたの朝、頭痛がありませんように』(現代書館)を出版した。
今の日本で、慢性疾患を抱えながら生きるとはどういうことなのか。何が自分たちをここまで生きづらくさせているのか。
著書の二人、難病を抱える弁護士、青木志帆さん(44)と、明確な診断名がつかない新聞記者、谷田朋美さん(44)に取材した。

『あしたの朝、頭痛がありませんように』を出版した弁護士の青木志帆さん(左)と新聞記者の谷田朋美さん(右)。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
社会との軋轢による居心地の悪さ
——こちら、ウェブでの往復書簡連載をまとめた本ですね。なぜ、二人でやり取りしようと思ったのですか?
青木 谷田さんが新聞で書いた「名付けられない病」についての記事を、私がXでたまたま見つけたのをきっかけに意気投合したんです。神戸のカフェで会うと、「慢性疾患と共に仕事をしている同じ年の女性」という共通項もあって、「病気あるある」で3時間も話し込んでしまいました。
私たちの病気は今のところ完治する見込みはないけれど、そう簡単に死ぬわけでもない。でも、元気でもない。そんな「グレーゾーン」の中にいるゆえに、生活のあらゆる場面で社会との軋轢を感じ、居心地の悪さを抱えながら生きています。
そんなモヤモヤを一人で書くよりも、近い境遇の人と対話するように書いた方がより深い話ができるような気がしたのです。
ちょうどその頃、哲学者の宮野真生子さんと人類学者の磯野真穂さんの往復書簡『急に具合が悪くなる(※)』(晶文社)を読んでいました。あの本をリスペクトしつつ、方向性の違う「似て非なるもの」ができるのでは、とぼんやり考えてもいました。
※転移したがんを抱え、急速に具合が悪くなっていく哲学者と、医療や命をめぐる現場を調査してきた人類学者が互いの人生に巻き込まれながら、生と死、出会いと別れから生まれるものを見つめて交わした往復書簡集。
——お二人は普段、どんな症状に悩まされているんですか?
青木 私は6歳の頃、脳腫瘍を摘出する手術を受けました。「下垂体」というホルモンが出る部位が傷ついたせいで「汎下垂体機能低下症」という病名がついています。

青木志帆さん(撮影・岩永直子)
基本的にあったりなかったりするのは頭痛です。生理が来るかな?ぐらいのタイミングで始まり、 生理が終わっても残っていて、毎月1〜2週間ぐらいは頭痛がある状況です。痛みを10段階で測るとレベル5ぐらいまでは平気な顔をして出勤し、それを超えてくると痛み止めを飲んで治まるのを待ってから出勤する。
また、心身へのストレスが重なると吐き気が出てきます。酷い時には15分に1回吐き、 それでも止まらなければ救急車を呼びます。
体温を調節する機能も弱く、寒すぎたら低体温になりますし、暑すぎたら高体温になります。
尿を抑えるホルモンが出ないので、薬を1日2回必ず飲むのですが、どうしても薬が切れるタイミングがある。 そうなると尿を一滴も残さず出そうとする。 頻尿になるし、きつい症状です。
谷田 私は医学的に確実な診断はついていないのですが、基本的に「頭痛」と「倦怠感」と「呼吸困難感」の「三大しんどい症状」です。24時間、365日ずっとあって、波がすごく激しい。生理前後や生理中、気温が急に下がったり上がったりした時や気圧の関係で、酷くなります。
呼吸困難感は春先と秋口が結構きつくて一番しんどく、吸っても吸っても空気が入っていかない感じがあります。
心臓は毎回不整脈ギリギリ手前ぐらいでいつも乱れているけれど、病気とまでは言えないと言われています。倦怠感は頭痛や呼吸困難に付随してひどくなります。
15歳の頃からこんな症状を抱えて生きてきました。
深刻に語らない「生存戦略」
——深刻な話なのに、お二人ともユーモアも交えながら書かれていますね。
青木 深刻なものを深刻に書くと、深刻にしかとらえられない。小さい頃からの生存戦略じゃないですけれど、人間関係をうまく続けていこうとするとどうしてもそういう言い方を選んでしまうのですよね。
谷田 病気の話を取り上げる時、デスク(新聞社で原稿を編集する人)に「しんどい話は誰も読みたがらないから」とよく言われてしまうのですね。それはそれで批判するべきところもありますが、青木さんがおっしゃるように、現実にそういう空気があることを感じてきました。
さまざまな方にアドバイスを受ける中で、自分自身も、チャップリンの「人生はクローズアップで見ると悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」という言葉は意識しました。ちょっと引いて見る。
ウェブの往復書簡の形として始めたので、そのままの手紙というよりは、人に見せるための手紙でもあるので、読みやすいようにという配慮もありました。
——連載のきっかけとなった谷田さんの新聞記事「記者の目」、名付けられない病があって、社会に理解されずに苦しんでいる人が数多くいることを世に知らしめる内容でした。寄せられた反響も本に載せていますね。
谷田 「こんな病気があることを知ってほしい」という書き方では、私が悩んでいることは捉えきれないと思っていたので、言葉を探すのは結構大変だったんです。
診断されることによって早急に物事に対応できる反面、それによって取りこぼされるノイズがある。でも慢性疾患の人間にとっては、その削られたノイズが困難の根幹だったりします。
心と体がつながっていることとか、社会の問題が発症や症状悪化につながっていることとか、精神疾患だけでなくあるものです。
でも診断されたとたん、その関係性が見えなくなってしまう。それをずっと感じていました。診断では、そのように、社会の中のいのちを丸ごと捉えることはできないこともあって、別の言葉が必要でした。
弱さをさらけ出さないと認めてもらえない
——弁護士さんも新聞記者も社会的には強者で恵まれた存在とされていて、ご自身でも強さと弱さがねじれていると書かれています。「こんなに困っている」と書きにくいところもあったのでは?
青木 患者会に何度か顔を出したことがあるのですが、頭の手術をして、知的に障害がある子もいるし、同じ土俵で語り合えるかというとそれは難しい。
病気はあったかもしれないけれども、ここまで弁護士として生きてられているのは、大学に入れてもらえているし、「実家が太いんですよね? 環境に恵まれていたからでしょう」と言われますし、そこについては反論のしようもない。
そんな立場で、「私、病気なんです。困っているんです」と一人で言うのは難しいので、新聞記者という強そうな肩書きの人と2人だったら言えるかな、責任分散できるかなととんでもないことを考えました(笑)。それでようやく書けるようになったわけです。
谷田 新聞記者は社会的には強者だし、病者は一般的に弱者とされますね。ただ、私は、自分の恥や非や人を傷つけたこと、差別してしまったことに向き合えないことを弱さだと思っているんです。
この本でもう一つ書きたかったことは、病気を抱えていて亡くなってしまった友人を私自身が傷つけたり、病気と共に生きていくうえで優しくしてくれる男性を利用したりした恥や非のようなものに向き合えるか。病者の立場で病気のことだけを書くこともできたけれど、そのことも考えようとしたところはあります。
——書くことは、普段は隠している自分の弱さと向き合う作業でもあったのですね。お二人とも、これまで人には話してこなかった痛みのようなものをかなり本の中で開示されていますね。
青木 そこまでやらないと、この問題に向き合えない、世間にこの苦しさを認めてもらえないという気持ちもありました。
私としては、不妊治療について書いた章が一番しんどかった。社会とのずれを一番感じた経験でもありました。その時は明石市役所に勤めていて、市長が子育て支援に舵を切った時と治療期間が重なった。「子供を産んで育てることが最上だ」という価値観が強い職場だったんですね。
職員の中には、私と同じように産めなかった女性も何人かいたのですが、役所の考える「共生社会」の中に私は入っていないという感覚はどうしてもあった。「子供を核とした街づくり」というのぼりがあちこちに立っている街だったし、明石に限らず少子高齢化の中で「子供は大事にしなければならない」というトレンドがある。
でも、「病人としての私を優しくしてもらった覚えがないのに」という思いもあって、「誰1人取り残さない」とか「共生社会」とか口にするんだったら、こっちも見てほしいという気持ちがどうしても浮かんでいました。
——その頃関わっていた「旧優生保護法違憲訴訟(※)」の東京高裁判決で、裁判官が「不妊手術をされたとしても、決して人の価値が低くなったわけでも幸福になる権利を失ったわけでもありません」と述べた言葉に救われた経験も書かれていますね。
※旧優生保護法に基づき、強制的に不妊手術を受けた障害者たちが、国に対して損害賠償を求めた訴訟。最高裁は2024年7月、原告側の訴えを全面的に認め、国に賠償を命じた。
「子供を産み、育て、幸せになる権利を一方的に奪った」という原告の訴えに接する度に、「子供が産めないと幸せじゃないみたいやん。そんなさみしいことを言うなよ」という気持ちに3%ぐらいなっていた。その気持ちに応えてくれたのが、あの所感でした。
ケアしてもらうのに自分を差し出したトラウマ
谷田 自分は記者の特権として、いろんな方のお話を聞いてさらけ出していただいてきたんですね。皆さんが自分の語りにくいところに向き合って、言葉にならないことを言葉にしようとされていることに私自身が感銘を受けてきた。取材を受けていただいた方に育てられたと思うので、自分について書く時は、覚悟を持って書かなければと思っていました。
一番きつかったのは、体調不良を抱えている中で助けてくれる男性に頼ってしまった経験を書くことでした。あの時、何にもなしでは助けてくれないと思ってしまったし、病人のケアは大変なので自分を差し出さないといけない、こっちもそれぐらいのものを提供しないといけないと思ってしまった。
そんな自分の「恥」のようなものは、一番書きにくいところでした。これをどう読まれるかは、正直本当に怖いところではあります。

——谷田さんは本の中で、「病んだからだで生きる私の『フェミニズム』についてことばにしていきたいものですね」と語りかけています。私はまさにこの部分がそうだと受け止めました。女性が何か困った時に助けを求めようとすると、女性としての自分を差し出さなければいけないと思わされてしまう。大事な問題を指摘していると思って読みました。
谷田 女性性を差し出してしまったことは病んだ経験の中で最も傷ついたことです。同時に、女性として当たり前に求められる気遣いや身だしなみなどがそもそも難しい中で、病者はより差別的な扱いを受けてもいます。作家の市川沙央さんは、芥川賞受賞作品『ハンチバック』で欲情されない体を書いていますよね。
なぜ病を明かしていいことはないのか?
——病気自体のつらさというよりは、病気を社会がどう受け止めてくれるかによる居心地の悪さを書かれています。病気や障害がある人に欠陥があるとする「医療モデル」から、病気や障害のある人を生きづらくさせている社会側の問題を改善しようとする「社会モデル」が言われるようになっていますが、まだそれは浸透していないですか?
谷田、青木 浸透していないですよね。
——やはり当事者が対処すべき問題とされている?
青木 司法試験に受かった時に、最高裁判所から「病気を治してから司法修習に来られないのか」と電話がかかってきた経験を書きましたが、その例は最たるものだと思います。あらゆる場面でそんな感じなんですよね。
——病気を明かしていいことはないと本の中で書かれていますが、オープンにするとどんな視線で見られてしまうのですか?
どんな病気であっても、慢性疾患のある人は、病気を明かしてろくな目に遭ったことがない人がほとんどのはず。そして、協力が得られなくても多少しんどい思いをしてでも、健康体のふりをしている方が、家庭から、地域から、教室から、職場から、排除されないんです。
青木 まず採用されないですよね。私が受けた頃は3回目までしか司法試験を受けられなかったので、3回目を受ける時、落ちたら後がないから公務員試験も受けたんです。ところが面接で、「なんで弁護士にならなかったんですか?」と聞かれて、病気のことを無防備に話したら、サーっと引いていくのがわかりましたね。
また、法律事務所などの採用試験の時に、能力的に高い点数をつけた人材も、前職でうつ病休職したことなど病気の経験がわかると採用しない、という話はよく聞きました。
谷田 私もメディア関係で病気を理由に採用しなかったという話は聞いたことがあります。
——優秀な人であっても、なぜ病気があるとシャットアウトするのだと思いますか?
谷田 「優秀」の評価が狭いですよね。新聞社で言えば「夜討ち朝駆けできないな。体力ないとできないでしょ」みたいな感じですね。それと、仕事のカバーなど業務を増やされそうだな、突然倒れて足を引っ張られそうだな、非効率だな、という風に思われるのでしょうね。
——今では企業も役所も「共生社会」や「多様性」を掲げていますよね。社員が途中で病気になることだってあります。でも最初から色々な配慮をしなければならない人を雇いたくはない?
青木 やっぱり真っさらなものが欲しいんですよね。 同じ点数で並んだ場合、片方は一病ある、片方は病気ひとつしたことがないとなると、真っさらな方を取りたくなるんだろうなとは思います。
弁護士の求職活動をした時もそういうことはありました。どうしても志望動機に関連するので言わざるを得ないのですが、本当に採用されない。記者や弁護士は「体力オバケ」の職業なので、無理がきかない、踏ん張りがきかないところがどこかに見えてしまうと難しいのでしょうね。
谷田 就職もそうですし、結婚もそうですよね。 予測やコントロールが不可能であることに対して、リスクであると感じられてしまうと差別されるのかなと思います。
社会に受け入れられる弱さと、そうでない弱さの線引きは?
——新聞社も、そういうマッチョな価値観の集団になっているから見放されてきているんだと思うんですよね。1つの事象を見るのに、さまざまな視点を入れたほうが絶対に豊かになるのに。谷田さんは、本の中で「社会に受け入れられる弱さと、そうでない弱さがある」と印象的な言葉を書かれていました。その線引きってどこにあると思いますか?
就職試験では学校でいじめられたこと、友人が自死したこと......私がそれまでに直面した「弱い」とみなされる出来事を聞いてもらうつもりで臨みました。何しろ新聞社は「弱者の味方」を標榜しているのだから。ただし、病気のことだけは決して話しませんでした。説明できることばがなかったですし、仕事に挑戦する前から「仕事は無理だ」と判断されることを懸念しました。その頃には、社会に受け入れられる弱さと、そうでない弱さがあることを明確に意識していました。
谷田 まさに今話したように、リスクであったり、将来の見えなさであったり、自分に現実的な負荷がかかると思われた時に排除されますよね。結婚や就職では特にそうですが、別の場所で会っていたらもしかしたら友達になれたかもしれない人でも、そういう場面で差別されてしまう。
ただ、当人たちは「恐れ」として感じているのではないでしょうか。企業で普通に働けることを見せていくしかないと思って働いています。

撮影・岩永直子
青木 「かわいそう」と思っていれば済む弱さと、それに対して何か行動を求められる弱さがありますよね。
人は「弱さ」の前で「どうにかしてあげなきゃならないんじゃなかろうか」、という気分になる。その時、子ども食堂のように、何をしたらいいのかわかりやすい場合は対処しようという話になりやすい。
でも、「私、しんどいんです」と言われたら、「なんかしてあげた方がいいのだろうけど、何をしたらいいかわからない」となる。どうすることもできないタイプの弱さなんですよね。そうなると、たぶん、何もできない自分を責められている気分になるんだろうなと思います。
私の父親がそういう人で、私が「しんどい」と言ったら、すごく機嫌が悪くなる人でした。 「どうすればいいかわからない」という気持ちをどう表出していいかわからないから、戸惑っていたのだろうなと思います。
私自身も、視覚障害の方と一緒にご飯を食べると申し訳ない気持ちになるんです。お皿を時計に例えて、「何時の方向に何があります」とスッとサポートできる人もいます。それが私はできないので、何もできずに横で食べていると、すごく責められている気分になることがある。
それと同じで、「何かしてあげたほうがいいのに、どうしたらいいかわからない存在」はすごく戸惑うだろうなぁと思います。責められているような気分になるのだろうし、何もできない自分を見たくない。
実際は、責めていないんですけれどもね。
(続く)
【青木志帆(あおき・しほ)】弁護士、社会福祉士
2009年、弁護士登録。2015年に明石市役所に入庁し、障害者配慮条例などの障害者施策に関わる。2003年に退職し、現在は明石さざんか法律事務所に所属。著書は『【増補改訂版】相談支援の処「法」箋—福祉と法の連携でひらくケーススタディ—』(現代書館)、共著に日本組織内弁護士協会監修『Q&Aでわかる業種別法務 自治体』(中央経済社)。
【谷田朋美(たにだ・ともみ)】毎日新聞記者
主に難病や障害をテーマにした記事を執筆。15歳頃から頭痛や倦怠感、呼吸困難感、めまいなどの症状が24時間、365日続いている。立命館大学生存学研究所客員研究員。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績