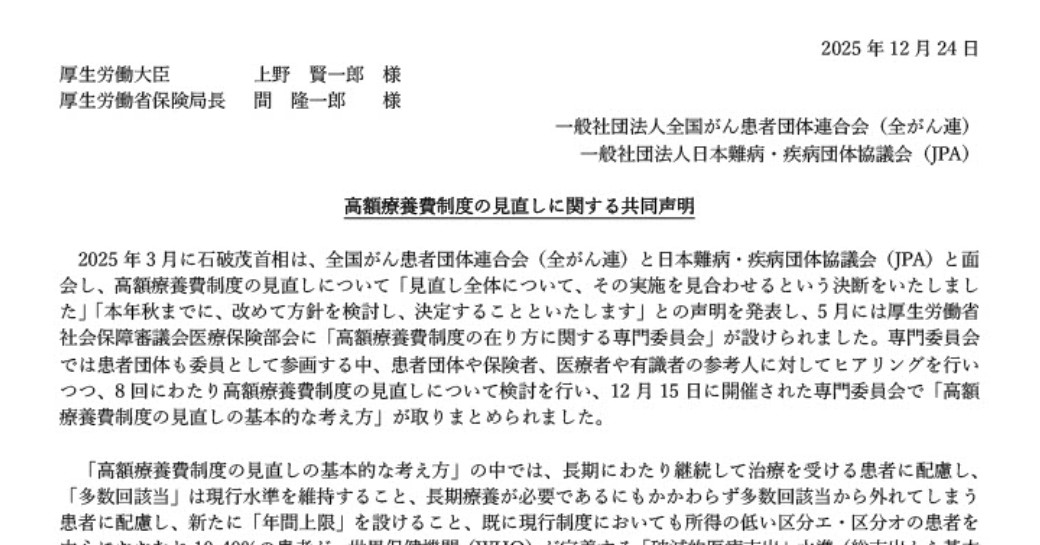「私の病気を理解して」に込められているのは、「私を排除しないで」という想い
慢性疾患と共に生きる弁護士と新聞記者が、社会の中で感じる居心地の悪さを語り合った著書『あしたの朝、頭痛がありませんように』(現代書館)。
この生きづらさを解消するためには、何が必要なのでしょうか?
弁護士の青木志帆さん(44)と新聞記者の谷田朋美さん(44)のインタビュー、後編です。

青木志帆さん(右)と谷田朋美さん。二人とも仲良く、おしゃべりが止まらない(撮影・岩永直子)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
「タニマー」 言葉を獲得することの意味
——この本で使われている言葉で面白いものがいくつかあって、青木さんが発明した「タニマー」(制度の谷間に落ちて誰も助けてくれない人)というのもその一つですね。
青木 難病患者への救済策への少なさについて訴えた時に作った言葉なんです。制度の谷間であると共に、関心の谷間でもある。ここに光を当てようと思って作ったのですが、この本もその試みの一つだと思います。
この連載を始める時に、「いくつか谷間があるよね?」という話をして、関心と認知と制度といくつか出てきたんです。
私は病名がついているけれど、谷田さんはまさしく病名さえついていなかったから、余計、把握しづらい。病名がないと、どういう病気なのか調べようにも取っかかりがないので、たいしたことないと思われるか、めんどくさいと思われるか、どっちかしかない。
——この本は「タニマー」を谷間から引き上げているのですね。制度を変えるのはすぐには難しいかもしれないから、まずは関心の谷間から引き上げようということでしょうか?
谷田 山で道に迷った時は、頂上を目指せといわれますよね。谷間に落ちると、本人が谷間に落ちていることに気づけず、遭難するからです。 ある程度上がってくると、自分が谷間にいたなとわかるのですけれど。「苦しいけど、どんな状況なのか分かんない」というのが谷間なんですよね。
だから、自分の言葉で経験を語り直すことが、ある種の回復のように私は感じています。医療として治すというのとは違うのですが、言葉で語ることによって、「怠けている」とか負のまなざししか受けていなかったところから、そうではないんだというところまで行けたと思います。

谷間にいる人たちって、本当に言葉がないんですよ。 「ヤングケアラー」や「宗教2世」もそうですね。社会になんとなく認知され、少しずつだけれど関心を持たれるようになった。
ただ、名指すことばは新たなレッテルになることも指摘されています。私も記事で「名付けられない病」と自分のことを書いたのですが、そのことばはいつでも捨てられるというか、孤立していたところから、仲間に出会えることが大事なのですよね。言葉によって、つながる糸口ができることがやっぱり大きいです。
なぜ仲間とつながることで救われる?
——自分だけではないと思うと、なぜ救われるのでしょうね? 青木さんと谷田さんは職業も病の状況も全然違いますが、つながったことで気持ちが軽くなるのはなぜでしょう?
青木 つながって何がいいかと言えば、積極的な傷の舐め合いができるからですね。 前向きな舐め合いです。「難病カフェ」(※)を考えた人は天才だなと思います。
※様々な難病の当事者が会議室やカフェで語り合うイベント。
新型コロナウイルスが流行り始めて多くは解散してしまいましたが、九州から始まって一時は全国に飛び火して流行りました。それまでは患者会が、当事者が集まって話をする場としてはオーソドックスだったのですけれど、私の場合、同じ病気の人とは状況が違い過ぎてなかなか思うように話せないところがありました。

青木志帆さん(撮影・岩永直子)
でも難病カフェは、基本的に自分は難病だと思っていたら誰でも参加していい。病名がついているかどうかもわからないような人も来るわけですが、似たような状況の人が中にはいて、その中には働いている方もいる。そして、働く上での苦労話はだいたい共通します。
論点が病気をどう治すかではなく、この病気と一緒に社会とどう折り合いつけていくかという方向で、病名を取っ払ってつながれる。このテーマで積極的に傷の舐め合いができる場だったんです。
谷田 私は、会社に黙って仕事をしてきたことにずっと罪悪感を抱いてきたんです。でも、「こんな状況でも働いてる人がいるのは希望だ」と言ってもらうと、自分に対する認識が変わってきて、自分が自分を見る目が変わるんですよね。 すごくプラスに自分を捉えられるようになった。それまで、「全然ダメな人間」だと自分でも思っていたのに、エンパワーされた。
一方で、新聞記者としては、社会をしっかり見てきたのかという反省も感じましたし、同じような病気の人はいっぱいいるのに、そういう人たちに届くようなものを書いてこなかったということにも気づかされた。でも、それさえもエンパワーなんですよね。
医療の言葉では救われない
——医療に対する批判も書かれていて、医療の言葉では癒されないことについても書かれています。私は自分が書いている医療記事と重ねながら読んだのですが、ワクチン接種後に体調不良を訴える患者に対して医師が「ワクチンとは関係ない」とただ突き放したり、依存症の人たちに対しても「だらしない」「自己責任」という視線で見たりすることで、患者さんが余計症状をこじらせてしまうことがあります。
谷田 依存症では、本来治療が必要な人が罰せられるような状況もありますね。
病気と一言でいっても、「大事にされる疾患」「蔑ろにされる疾患」があることをずっと感じてきました。
がんなどは二人に一人がなる時代ですから重視されますが、病気のヒエラルキーを何が決めているかといえば、これは複雑な糸を丁寧にひもといていくような作業が必要なのでしょう。ただ、医師は現代医学の権威ですから、やはり重要な存在です。
日本在宅ケア学会の学術集会に行ってきて、ある医師が「エビデンスを積み重ねて、それに基づいてきっちりやれば必ず良い医者になれる。 だけど、最良の医者にはなれない。最良の医者になるには、サイエンスとアートが必要だ」と言っていました。
——アートって何でしょうね?
谷田 アートについては、「患者の生活であったり、人生であったりをどういうふうに捉えるか、それをどうケアするか」というようなことをおっしゃっていました。
私は終末期医療に何かヒントがあるような気がしています。終末期医療は、治らない時に医療に何ができるのかをずっと考えてきた分野だと思います。慢性疾患も多分、終末期医療と同じで、診断して治すというだけではないものが必要なんですね。

谷田朋美さん(撮影・岩永直子)
とはいえ、忙しい医師も多いですし、現代医療だけに任せるものでもないのだろうなとは思っています。この本は、診療所でなされてきた病の対話を、診療所の外にもっていく試みでもありました。
——私も医療取材の出発点が終末期医療だったので、治らない病気とどう折り合いをつけていくかに強い関心があります。ただ、本来の「エビデンス・ベースド・メディスン(Evidence-Based Medicine 、エビデンスに基づく治療)」の定義は、現時点での最良のエビデンスと患者を診る医師の専門性を組み合わせて、目の前の患者に最良の医療を提供する、というものなのだそうです。でも臨床研究の結果を個人に機械的に当てはめるような冷たい印象になっていますよね。そして、慢性疾患こそ、エビデンスに基づかない怪しい医療が入り込みやすそうですね。
谷田 怪しいかどうかの評価はさておくとしても、エビデンスが整わない医療はままありますね。これまでにいろんな診断名を告げられては、他の医師に否定されるということを繰り返してきました。
28歳で診断された「脳脊髄液減少症」もそうですね。私は15歳の頃に調子を崩しましたが、ちょうどその年に交通事故にあっているんです。脳脊髄液減少症は主に交通事故で発症することで知られています。実際に髄液がかなり漏れているという検査結果も出ましたが、この病気に対しては否定的な医師も少なくなく、私には今のところ判断ができないんですよ。
そういうこともあって、自分では「医学では明確に説明がつかない症状」だと言っています。説明になっているのか分かりませんが......。
——原因はとりあえずさておいて、その苦しさに対応してくれるお医者さんがいるといいですよね。
谷田 症状ベースでとりあえずなんとかしてくれる人がいてくれるとありがたいですね。 今は耳鼻科にかかっているのですが、症状に応じて薬を出してもらってなんとかやってきました。
「内側から感じるからだ」を軽視しないで
——医療との接点で言えば、「内側から感じるからだ」という言葉を使い、医療がそれを軽視することがつらいとも語っていらっしゃいますね。
「内側から感じるからだ」がなかったことにされることが最もつらい経験だと感じてきたんです。(中略)まずその人自身が感じる「からだ」があるはずなのに、客観性の名のもとにすべてが数値で切り落とされて、本人の痛みや感覚がなかったことにされていく、ということです。診断とは、本来「内側から感じるからだ」に対して、後からくるもののはずなんだけど、医療の現場では一方的にそちらだけが事実だとされることが多くて、「内側から感じているからだ」がそれよりも下のものだとみなされていると感じてきました。
谷田 本書で鼎談してくださった村上靖彦・大阪大大学院教授がご著書「客観性の落とし穴」の中で「内側から感じるからだ」という表現をされていて、それを使わせてもらいました。医師がそれを聞いてくれるだけでも、ちょっと違ってくると思います。痛みって医療の世界では結構軽視されていませんか?
——診療科によって違う気がしますね。
谷田 ペインクリニックとかは確かにありますね。ただ、痛みの治療の選択肢はまだ限られていると感じるので、もっと研究が進んでほしいですし、保険適用できる治療や対象疾患も広げてほしいなと。医師には、患者が内側から感じるからだについてもう少し耳を傾けていただいて、かつ軽視しないでほしいのですが、難しいですね。
青木 それは医師もおそらく責められている気分になるのだと思うんです。医療は患者の病気を治すことが最大のミッションだと思いますが、そう簡単に治らない、でもどうにかしてほしい、という患者はめんどうくさいだろうな、と今ならわかります。
合理的配慮を受けるためにどうしたらいいのか?
——青木さんは「障害者差別解消法」の専門家でもあります。この法律では、障害者側が社会の壁を取り除くよう求めたら、過重な負担でない限り対処する「合理的配慮の提供」が役所や事業者に義務付けられました。逆に病気であることを明かすと排除されてしまうことを「合理的排除」と皮肉を込めて表現していますが、慢性疾患のある人の場合、どんな合理的配慮が必要なのだと思いますか?
青木 私も市役所で管理職をしたことがあったのですが、私のような先の読めなさを抱えている職員をマネジメントするのは大変だなと気づいたところがあります。
自分としては、とりあえず、「これだけ配慮してくれたら、人並みにできる」ということは幼い頃から言語化して伝えるようにしてきました。「合理的配慮」については、段差があるところは車椅子が通れない、じゃあスロープを作ろうというのはわかりやすい。

青木志帆さん(撮影・岩永直子)
でも慢性疾患の体調の悪さにどう配慮すべきかは、まだ研究が深まっていないのでは、と思います。
患者側も「しんどくなることがあるので、なんとなく大目に見てくださいよ」ではいけないことがわかるので、当事者側ができるだけわかりやすく伝える必要があります。
ただ、同じ説明をしても、理解できる上司とそうでない上司はいる。役所だと上司はコロコロ変わりますし、学校も毎年先生が変わりますよね。全員が理解するの絶対無理なので、「合理的配慮を尽くせ」の一言ではなかなかうまくいかないだろうとも思っています。
精神疾患の方からのご相談も受けることがあるのですが、「あなたに必要な合理的配慮は何ですか?」と聞いても、明確に答えることが難しい人はいます。このように、病気と合理的配慮は、まだまだ難しい課題が多いと感じています。
個人の努力だけでは難しい 支える人も評価される社会に
——今回の本では、慢性疾患を抱える自分達と、社会とのズレのようなものをさまざまな角度で書いていますが、それを解決する策を考えるのはまた難しいのですね。
青木 自分たちでも、そんなに簡単には提示できなくて。どういう配慮をしてもらったら楽になるかを本人と共に考える専門性がどこかにたぶんあるはずです。そういう専門職が必要なのだろうと思います。
例えば、厚労省ががんや難病の仕事と治療の両立支援をするコーディネーターの育成をやっています。あれは一つの専門性だと思います。そうやってセルフアセスメント(自身の状況を客観的に評価すること)をしないと、なかなか合理的配慮を提供してもらうところまで行き着けないんですよ、と講演などで言っているのですが、具体的にどうやっていくかは難しいと思います。
谷田 セルフアセスメントは当事者1人でやるのは酷だと思っています。私の場合は、自分と組織の間に入って調整してくれる先輩がいた時は、結構働きやすかったんです。たとえ必要な配慮を正確に伝えることができたとしても、相手に知識や余裕や聞く耳がないと伝わらないこともありますよね。
慢性疾患の人はクビになることも多いのに、なぜ自分は働いてこられたのか考えると、1つは仕事が好きだったし、裁量労働制に近いので自分で仕事を調整しやすかったという仕事のマッチングの問題もあります。
もう一つ大事なのは、組織の理念ですね。 合理的配慮については、私の会社は全然浸透していないと感じますが、「弱者の味方」「社会の公器」といった意識はとても強い。社員に対してもそうあるべきだと考える人に支えられてきたんですよね。
そういう人に支えられたという思いがあるから、私も体調を崩した後輩たちのことはずっと気にかけてきました。
実際、誰しも弱ることはありますよね。この人にだったら相談できる、という存在が組織にいることは重要だと思います。
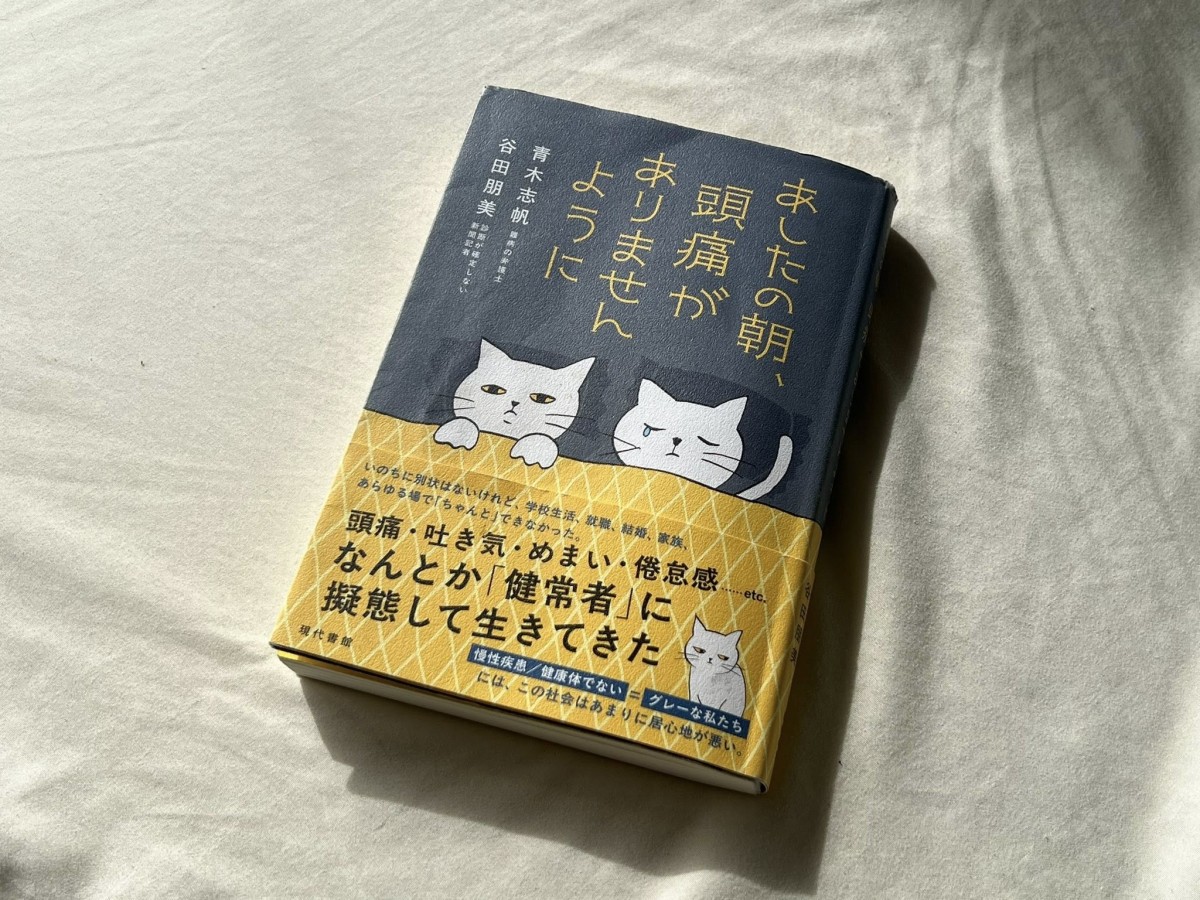
——そういう人って属人的になっていて、システムとして確立していないですよね。
谷田 そうですね。運です。自分もマイノリティーとして苦しんだ経験がある人が、そういう存在になっていると感じます。そして、あまり出世しないような人たちですよね。
——そういう意味では、病む経験や弱った経験は組織運営の中ではマイナスにはなっていなくて、むしろプラスに働くこともあるわけですよね。
谷田 そうなんです。だから、個人の努力ももちろん必要なんですけれど、これだけ多様性やダイバーシティが組織に必要だと言われる時代なのですから、それを組織に活かすにはどうすればよいのか、管理職が学んでほしいと思います。少なくとも、そういう企業しか、若い人からは就職先として選ばれなくなっていくのではないでしょうか。
私は病気を隠して入ったので、健康な人と同じレールに乗って評価されます。「谷田さんは夜討ち朝駆けとかできないから入れてあげない」ということは結構言われ続けてきました。健常者にとっての公正な競争は、我々慢性疾患の人間にとっては決して公正ではないので、そこのレールで評価されるのは難しい。
日本の組織は体力勝負ですごく頑張ったご褒美として、希望の部署に異動させるという文化があります。病気の人はそういう文化の中では生きていけません。そうではない評価の形があれば、病気の人ももっと活躍できる場があると思っています。
「私の病気を理解して」は「病気の私のそばにいて」
——青木さんは「私の病気を理解して」という言葉の中には、私を排除しないでほしいという願いがあると書かれています。病気そのものを理解してもらいたいわけではなくて、一緒に生きてほしいという意味なのですね。
私の、私たち難病者の「私の病気を理解して」という願いの中に込められていたのは、「私を排除しないで」という想いなのでしょう。(中略)完璧に理解してほしいのではなく、関心を持って、そばに居続けてほしい。「私の病気を理解して」というより、「病気の私のそばにいて」の方が正確でしょうか。
青木 例えば、患者は、24時間テレビ的なものとか、ドラマとか、ドキュメンタリーで取り上げられると、ものすごく喜ぶんですよね。「これで理解が進んだ」と。その気持ちはわかる一方で、何を理解してほしいのかって解像度を上げていくと、よくわからないですよね。
私も、自分の病気について誰かに理解してほしいかというとそうじゃない。それでもなお理解してほしいという言葉が出てくるので、この気持ちは一体何なんだろうって考えた時に、やっぱり輪に入れてもらえるとか、排除されないことを求めているのだろうと考えています。
「私たちの病気を理解して」という言葉の本質に迫っていくと、私たちを排除しないでほしいというところに全ての疾患はつながっていくのではないのかなと思っているところです。
「傷つける」裏には「傷つき」が
——今の世の中の病気の人とか困っている人の不寛容さの影には、いわゆる「強者」の人もしんどいのにケアされていないつらさもあるような気がします。プレッシャーの強い激務を続けないと今の生活が維持できず、常に滑り落ちる不安にさらされている。自分はこんなに頑張っているのに、病気の人は甘えやがってと、自分のしんどさの裏返しもあるのでは?
谷田 本書に書きましたが、私も、亡くなった友人に「甘えているのでは。自分だけがつらいと思わないで」と突き放してしまったことがあります。
でも、そんな風に傷つけてしまったのは、私自身がケアされてなかったからなんですよね。
SNSで人を攻撃する人の内側にも、傷ついている自分がいるのではないか。傷つけることと、傷つけられることとは、本人の中でつながっていることも少なくない。だから私は傷ついた時、「誰かを傷つけていないか」とすぐに切り返せるかどうかを、自分の戒めとしてきました。
というと、「怒りを手放すのか」「そんなに自分ばかり否定しなくてよい」と誤解されるのですが、何に怒り、どう自分をケアするかを考え抜くということでもあります。自分の多面性と向き合うことが、不寛容から脱げ出す一歩になると信じているんです。
——そういう意味でこの本は、他者に見えづらい病気について語っているようですが、いろんな立場の人に刺さりそうです。自分のことして考えてもらえそうですね。

二人にサインをもらいました。「好きな言葉を入れてください」と無茶ぶりしたら、青木さんは「病気の私のそばにいて」、谷田さんは「弱さと向き合う」と書いてくれました。(撮影・岩永直子)
谷田 そうですね。私たちはつながることがケアになりましたが、ケアの方法はつながることだけではないと思います。ただ、非や弱さをどう見つめ、どう自分をケアし、どう社会に声を上げていくのか。そういうことを考えながら書いた本でもありますので、病気の人にはもちろん、多くの人に読んでいただきたいです。
青木 世の中の現在の最大公約数とずれている部分って、各人どっかしらあるんだと思うんですよね。 我々は病気でしたけど、私の同僚は子供が今、小1の壁に突き当たっていて、ものすごくしんどそうなんですよ。 仕事に集中できないのが、はたで見ていてもよくわかる状態です。
そういうしんどさは、 我々の慢性疾患のように通奏低音のようにずっと煩わされるものであるかもしれないし、ライフステージごとにあるのかもしれない。でもみんな、どこかしらで最大公約数とずれている部分を抱えながらどう生きていくのか考えているのだと思います。
だから、私たちの病気が一番しんどいというつもりは毛頭ない。お一人おひとりの足りない部分を代入して読んでいただけたらいいなと思っています。
(終わり)
【青木志帆(あおき・しほ)】弁護士、社会福祉士
2009年、弁護士登録。2015年に明石市役所に入庁し、障害者配慮条例などの障害者施策に関わる。2003年に退職し、現在は明石さざんか法律事務所に所属。著書は『【増補改訂版】相談支援の処「法」箋—福祉と法の連携でひらくケーススタディ—』(現代書館)、共著に日本組織内弁護士協会監修『Q&Aでわかる業種別法務 自治体』(中央経済社)。
【谷田朋美(たにだ・ともみ)】毎日新聞記者
主に難病や障害をテーマにした記事を執筆。15歳頃から頭痛や倦怠感、呼吸困難感、めまいなどの症状が24時間、365日続いている。立命館大学生存学研究所客員研究員。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績