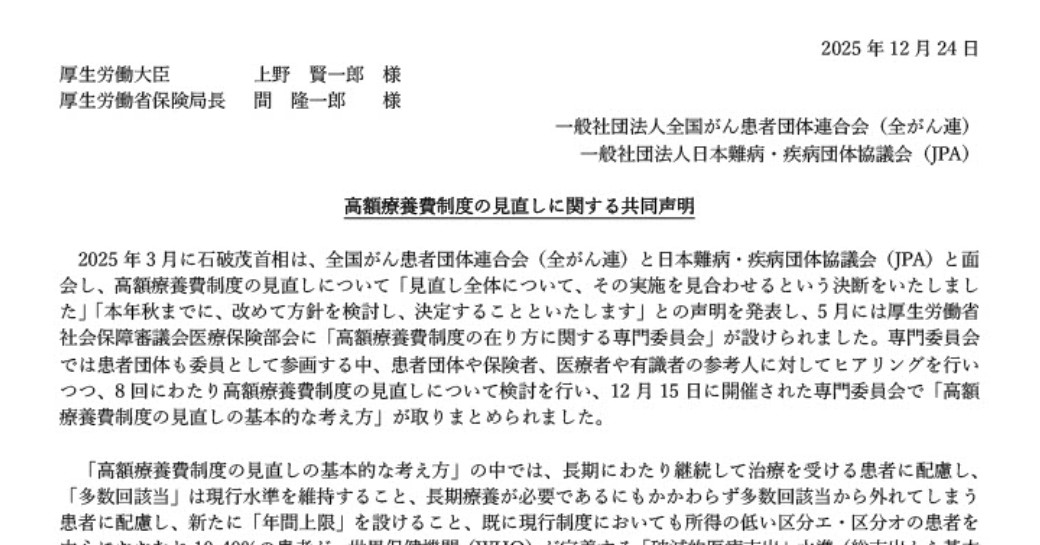緩和ケア医の僕が、なぜ生活に困難を抱えた子供の居場所作りに関わり始めたのか?
神戸市の緩和ケア医、新城拓也さんは本業のかたわら、ひとり親家庭や生活に困っている世帯の子供を支援するNPO「こどもサポートステーション・たねとしずく」の理事としても活動し始めた。
普段はむしろ高齢患者を相手にすることの多い医師が、なぜ子供支援に関わることになったのだろうか?
新しい道に踏み出したきっかけは、コロナ禍での経験だという。新城さんにお話を聞いた。

兵庫県西宮市に8月1日にオープンした、子供のフリースペース「たねとしずくライブラリー」の入り口に座る新城拓也さん
家事支援や学習支援、居場所作り
新城さんが関わる「たねとしずく」は、ひとり親家庭や生活に困難を抱えた家庭の子供が安心して子供らしく過ごせるように、さまざまな支援活動をしているNPOだ。
忙しく働く親の代わりに子供が家事やきょうだいの世話を抱えこまずに済むように家事支援をしたり、フードバンクや農家の協力を得て食料を送ったり、食事を無料で提供する「若者食堂」を開いたり、学生ボランティアの力を借りて学習支援をしたりしている。
8月1日には兵庫県西宮市に拠点となるフリースペース「たねとしずくライブラリー」をオープンした。全国に「一箱本棚サポーター」を募って子供たちに読んでもらいたい本と定額の活動費(月3000円)を寄付してもらい、放課後の子供の居場所にしてもらう。

新城さんが寄付した本箱。ジャズプレイヤーを目指す高校生を描いた漫画「BLUE GIANT」を置いている。「本の言葉は長く残って、じわじわとその人の人生に影響を与えていく。そんな1冊に出会ってほしい」。
普段は医師として働く新城さんは、理事会に出席して会の運営方針を一緒に決めたり、サポーターを連れてきて活動に巻き込んだりするのが主な活動内容だ。健康に不安を抱えた親を医療につなぐ手伝いもしてきた。
コロナ禍でのオンラインゼミで畑違いの支援者とつながる
新城さんが畑違いのこの活動に足を踏み入れたきっかけは、コロナ禍で自身が孤独に陥ったことからだ。
「2020年から新型コロナウイルスの流行が始まって、学会や講演会の現地開催もなくなり、閉じ込められたような気持ちになりました。人と全然交流ができなくなって、パニックになったのです」
救いとなったのは仲の良い熊本大学の哲学者、苫野一徳さんのオンラインゼミに参加することだった。
感染症の流行で生活のあらゆる自由が制限される中、政治はどうあるべきか、ケアとは何か、差別をどう考えるべきか。読書会を開いたり、有識者に講演してもらったりしては、議論を重ねた。
そこに参加していたのが、後に「たねとしずく」の代表理事となる大和陽子さんや李恭子さんだった。その時、二人は前身となる支援団体で、ひとり親家庭の家事支援や育児サポートを行なっていた。
「僕も彼女たちも違う分野ですが『ケア』について考えてきたので、一緒に議論すると面白い。僕は医療や介護の面からケアを見てきたのですが、NPOの人たちはフェミニズムの視点から見ていて、DVやモラルハラスメント、暴力の問題は避けられない。全く違う視点から違う言葉を投げかけられて新鮮な驚きがありました」
「ジェンダーや人権という言葉はニュースにあふれていますが、どうもとっつきにくい。それが彼女たちと話すと、ひとり親家庭の現場にそんな言葉はあふれていて、女性がずいぶん気の毒な目に遭っているということもよく理解できました」
自身の仕事を振り返ると、新しく診療する患者の情報をカルテに書く時、そんな視点では見ていなかったことに気づく。
「男性患者、配偶者あり」の場合、妻に「介護できますか?」と聞いて、「できます」と答えられると、「じゃあ、あまりヘルパーは入れなくても大丈夫ですね」と返してしまう。
「在宅医療の中に、女性の家事やケアが含まれた状態を当たり前だと思っていたし、ケアの担い手として妻を見ていたことに気づきました」
逆に女性が患者で、夫がいる場合はケアの提供者として見ていないこともある。
「『男だけど意外に料理ができる』とか、『子供が近くに住んでいるからケアの担い手として頼れそう』とみてしまう。日本の家族制度の中で家事やケアの負担を当然のように強いられ苦しい思いをしているのは女性だと気づかないまま診療していたのです」
「居場所作り」を一緒に
オンラインゼミのオフ会などもやって親しくなるうちに、新城さんは彼女たちが行ったアンケートをまとめるなど、徐々に支援活動に巻き込まれていった。
そのうち、「今までの支援活動だけでなく、居場所も作りたい」と相談されるようになり、理事としての参加を打診された。今年1月、設立したNPO法人で理事に名を連ねた。
「自分の仕事の延長ではない活動ですね。でも元々自分のクリニックを拡大することには関心はない。社会に還元したい、お返しをしたいと考えるようになった時に、『居場所作り』という新しい活動に関われるのは楽しそうだなと思ったのです」
阪神電車の西宮駅の近くに一軒家を借りて、「たねとしずくライブラリー」をオープンした。医師仲間らにも声をかけて、本棚のオーナー枠は80箱中20箱ほど埋まった。定期的に通う子供も増えている。

「たねとしずく」の主要運営メンバーと新城さん。左から保育士の李恭子さん、代表理事の大和陽子さん、保育士の金田美紀さん。医師だからと言って持ち上げることはなく「さん」づけで呼び合う、完全にフラットな関係性だ。
「そもそも生活に困難のある家庭に支援に入ると、家に本がないそうです。本を買うお金もないし、本を読む習慣もない」
「お金のある子はマクドナルドやスターバックスに行けるかもしれませんが、お金のない子は無理です。しかもそんな場所では大人とは出会えない。本があって、大人がいて子供たちの話を何気なく聞ける場所があったら、困りごとに手助けができるかもしれない。その子の可能性がひょっとしたら広がるかもしれない。そんなことを意識して活動しています」
2階は塾などに通えない子供のために学習支援をするスペースだ。新城さんの大学生の次男もボランティアで家庭教師を始めている。

大和陽子さん
代表理事の大和さんは医師である新城さんを仲間に巻き込んだことについてこう語る。
「医師として私たちが持っていない資源を持っているし、ケアの専門家ということで相談にのってもらえる。ご病気になられた親御さんと関わるときに専門的な知見をいただいたこともありました。気軽に相談できる医師がいるのはありがたい。拓也さんとは友人として関わっているから、医師の世界のヒエラルキーは通用しません(笑)」
本業で活かされるNPOでの経験 自身の居場所にも
本業とは違う活動を始め、新城さんは自分の人生も豊かになったと感じている。
「これまでつながりのある緩和ケアの医師たちとも、全く関係のない場所でつながり直せたのが良かった。コロナで人間関係が全部ストップして、こういう活動でもなかったら再会できなかったでしょう」
自分がこれまで医師として持っていた視点とは違う見方を持てたこともプラスになった。
「熱意を持って社会課題に取り組んでいる人たちに巻き込まれて、学び直して、違う目線で現場を見られるようになる。男性で医師で『自分は恵まれて選ばれて優秀だ』と自分の力を過信しているところがありましたが、ここではその『権力』は通用しません。かなり釘を打たれて謙虚になれました」
ここで身につけたそんな姿勢は、本業でも生かされている。
「より注意深く言葉を選ぶようになりました。例えば、患者さんに対して『何か話したいことはありますか?』『何か手伝えることはありますか?』『何か手助けしてほしいことはありますか?』と意識して相手が話しやすくなるような声かけをしています」
「医療の文脈でこちらが欲しい情報を答えさせるのではなく、相手が今、一番困っていることを話してもらう。幅を広く取って、なんでも語れるようにする。そういう聞き方をしないと本当に困ったことは出てきません。それを繰り返すうちに患者さんはスッキリする。気持ちを受け止めてもらえたと感じると、結果的に症状も良くなっていくのです」
自身の努力と実力が重んじられる医師の世界とは違う人間観の中に身を置けるのも嬉しいことだ。そして、困難を抱えている子供にこそ、そんな人間観に触れてほしいと願う。
「僕は『PDCA(Plan計画、Do実行、Check評価、Action改善)サイクルを回す』という考え方が大嫌いなんです。計画したとしても今の世の中は不確定な要素が多すぎますし、この言葉は『何もかも自分の能力と努力次第。それしか頼ることができない』という考え方に近い。でもそんなことはない」
「僕もこういう団体と出会うと、違う方向からものが見えて少しずつ状況が変わっていく。そんな偶然の出会いがない世界はあまりにも希望がない。偶然の出会いが自分を変える可能性を僕自身、信じたいし、人と出会わない限りは偶然は起きません。たねとしずくもそんな場になってほしいと思っています」
この活動は、コロナ禍で人とのつながりが制限され、気持ちが不安定になっていた新城さん自身の救いにもなった。
「一つのプロジェクトがあって、それを実現するための彼女たちとのおしゃべりがあって、自分の止まっていた時間も動き始めた感じがあります。非常に癒されました。子供たちのために作った居場所ですが、僕自身の居場所にもなっていると思います」
クラウドファンディングや寄付も募集中
たねとしずくでは9月末まで2階の自習室を整備するためのクラウドファンディング「中高生が無料で自由に使える自習室を作りたい」を行なっている。寄付サポーターの応募はこちらから。
【新城拓也(しんじょう・たくや)】しんじょう医院院長
1971年、広島市生まれ。名古屋市育ち。1996年、名古屋市大医学部卒。社会保険神戸中央病院(現・JCHO神戸中央病院)緩和ケア病棟(ホスピス)で10年間勤務した後、2012年8月、緩和ケア専門の在宅診療クリニック「しんじょう医院」を開業。著書に 『患者から「早く死なせてほしい」と言われたらどうしますか? (本当に聞きたかった緩和ケアの講義)』(金原出版)『「がんと命の道しるべ」 余命宣告の向こう側 』(日本評論社)『超・開業力』(金原出版)、共著に『不安の時代に、ケアを叫ぶ:ポスト・コロナ時代の医療と介護にむけて』(青土社)がある。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績