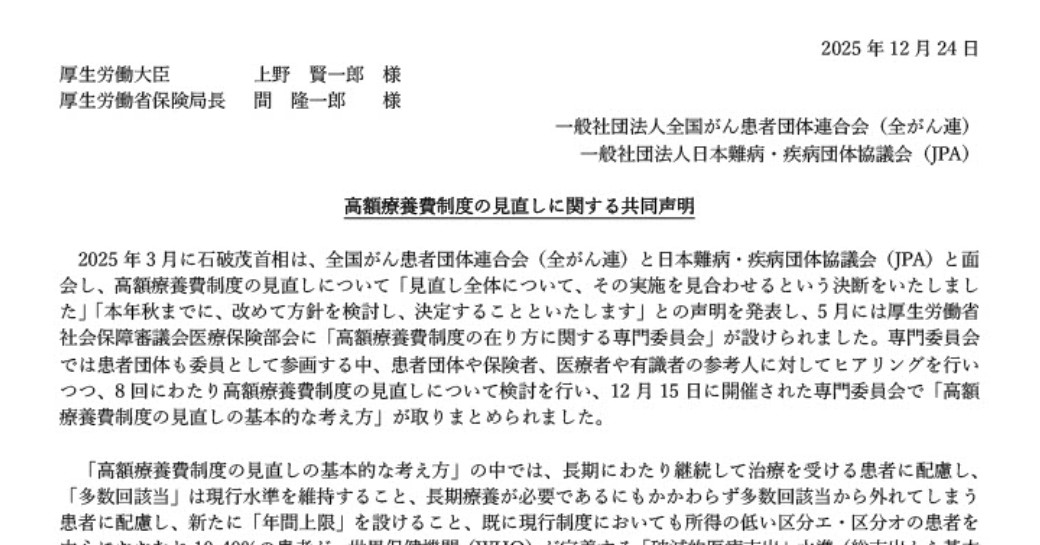母がALSになって家族の生活は一変した ヤングケアラーだった僕があの時、欲しかった情報
法政大学現代福祉学部2年生の南光開斗さん(20)は、小学生の時に母(54)がALS(※筋萎縮性側索硬化症)になった。
母を介護する中で、難病の人が生きやすくなり、介護者が楽になるための情報が絶対的に不足していることを知る。
そんな南光さんは今、難病を生きる当事者や周りの人に情報を届けるための仕組みを作り始め、起業を目指している。
これまでの歩みを聞いた。全2回。

南光
※手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん動かなくなっていく進行性の神経難病。治療法がまだ見つかっていないが、人工呼吸器や胃に開けた穴から栄養を補給する胃ろうなどを作って長く生きられるようになった。体が動かなくなっても感覚や内臓機能などは保たれる。
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
小学5年生の時に母がALSを発症
母の体調に変化が現れたのは、自身が小学5年生の時だった。
看護師だった母は当時45歳。大きな荷物を持った時に肩を痛めた時、手も動かしにくくなり始めた。肩を痛めたせいかと思っていたが、病院に行くとどうも肩とは無関係だ。医療者として心当たりのあるALSの検査を受けて、数ヶ月後に確定診断を受けた。
「患者さんを間近に見ていた母が、『これだけは怖い』と最も恐れていたのがALSだったようです。最初は信じたくもなかったぐらい衝撃は強かったと聞きました」
当初、両親は自分や3つ上の兄、5つ下の妹ら3人の子供に病名を隠そうとしていた。
「体に力が入りづらい難病であると説明されていましたが、治るものだと思っていました。治療してくるねと言われて、家にいない時期があることも納得していました」
ところが症状はどんどん進み、歩行器なしでは歩けない状態になっていく。父は仕事に、自分たちは学校に行く日中、もしもの時に緊急通報できるようにしてあった。救急救命士が駆けつけた時に呼吸困難になっても延命はしないという意思表示の文書も用意していた。
子供たちに隠していたその意思表示の文書をある日、兄が見つけた。「病名はALS。延命はしない」と書かれていた。
兄は大泣きしながら母に「これどういうこと?」と問いただした。自分は何が起きているのかわからない。ただ「相当やばいことが起きている」という不安が襲った。
その日の夜、両親から初めて病気の説明を受けた。
「母は申し訳なさそうな顔をして、涙を流しながら説明してくれました。兄は病名を見つけた時からネットでこの病気のことについて調べていたので、兄がひたすら問いただしてそれに答える形でした。症状が進んでも人工呼吸器をつけるつもりはないと言っていました」
急速に症状が進む母とヤングケアラーだった自分
病の進行は早かった。あっという間に全身が動かなくなり、発症から1年も経たずにベッドに寝たきりになった。
「その頃にはちゃんと喋ることもできなくなって、僕が小学6年生の頃には、ボタン式の意思伝達装置を使うようになっていました」
その数年後にはボタンを押すことも難しくなり、50音の描かれた文字盤を目で追って介護者が言葉を拾う方法や、決まり文句の書かれた文字盤を見せて目の動きで選んでもらう方法で、意思疎通を図った。
仕事のある父や、受験に忙しい兄、まだ幼い妹に挟まれて、家族で協力しつつも、自分が長時間の介護を担った。
「家族には『お前は頼りになるわ』と言われるし、父を知る地域の人たちからは『南光先生の息子は偉いな。真面目だな』と頑張れば頑張るほど褒めてもらえる。勉強も剣道部の活動も両立しつつ、帰宅してからは胃ろうのケアや体位交換や着替えなど、母の介護も並行して頑張りました」
介護は夜間も休みの日も続いた。
「寝室に行ってからも、アラームが鳴ったら起きて世話をしにいくこともありました。特に夏休みなどの長期休暇の時は、北海道から手伝いに来てくれた母方の祖母と僕がメインで介護していました」
母の感情失禁で家族仲も一時不穏に
しっかりもので優しかった母は、病気で日々自分のできることが少なくなっていくことに、家族も想像できないような葛藤や苦しみを抱えていた。さらに南光さんが小学校、中学校の頃、ALS患者に出やすい感情失禁や情動制止困難(※)といった症状がかなり長く続いた。
※感情のコントロールができなくなる症状。
「呂律が回らないけれど、泣き声だけは出る時期には、ちょっとした刺激で大泣きされてしまいました。その泣き声には怒りも含まれているように聞こえます。これまで僕らが聞いたことのないような全力の声で、怒号や号泣が続くことがありました」
多い時はそれが5分に1回ぐらい、頻繁に繰り返された。号泣しているうちに呼吸困難に陥ったりもした。
「1回そういう状態になると、止められなくなります。自分たちが介護をミスした時もなりますし、関係ない時にもなる。母の方が無茶を言ったり、こちらの言ったことを誤解したりして起きる時もある。逆にこちらが誤解して怒らせたこともあります。とにかく毎日、限界を超えた母と家族の怒号の応酬が続いて、たまりませんでした」
仲が良かった家族関係が一時、それで危うくなることもあった。
「自分も怒りのまま言ってはいけない言葉を母にかけてしまったことがあるし、他の家族がそう言うのを聞いたこともありました」
そういう状態が続くと介護が進まないため、なるべく母の気持ちを逆撫でしないよう、腫れ物を触るような対応になっていく。
「自分が介護している時に、他の家族が母の気持ちを逆撫でするようなことを言うと、家族に対してもめちゃくちゃイライラしていました。『俺が介護しなくちゃいかんのに怒らすなよ!』と。全部が嫌になるし、全部が嫌いになるし、最悪の状態が続いていました」
そんな時期になんとか生き延びることができたのは、母の教えと、ギリギリのところで介護から逃がしてもらった経験が大きい。
母は落ち着いている時に、「これは感情失禁という症状なの」と言って、「これを今すぐ読んで!」と当事者のブログを示して、病気ゆえの症状だと何度も教えてくれた。
「当時は幼くて完全には理解できませんでしたが、母がこんなに泣き叫ぶのは病気のせいだとはわかりました」
また、家族を休ませるためのレスパイト入院やコロナ禍での入院で、母の介護から離れられたことが自分を救ってくれたところもある。
「どうしても介護でしんどくなった時に、ケアラーが逃げたり、考えなくて済むような状態に置かせてもらったりすることはすごく大事なことだと思います。もちろん逃げずに立ち向かったり、乗り越えたりする人はかっこいいんですけれども、そうできない介護者に休憩を与えることは必要だと思うんです」
起立性調節障害になり、不登校に
そんな毎日が続いていた中学2年生のある朝、突然、起きられなくなった。自律神経の働きが悪くなり、起き上がると脳や心臓に十分血流が巡らない「起立性調節障害」と診断された。それまで全力で走ってきた心がポキンと折れたようだった。
そこからほとんど学校に行けなくなった。
「友達との関係もこじれて、どんどん孤立していきました。友達との話し方や笑い方もわからなくなり、人と関わること自体が辛くなりました。すごくしんどかった」
この不登校の状態は中学3年まで続いた。
もっと早く知りたかった、コミュニケーションの手段
その間も、母が言葉を伝える方法はどんどん狭まっていった。
「自分が中3の頃に、父の友人から初めて視線入力の装置の存在を教えてもらって試しました。でも、その時には既に目が少し動かしづらくなっていたし、目が自由に動く時から練習やルール決めをしていたわけではないので、使いづらさもあって誤解が生まれて喧嘩になることもありました」
「自分以外にパソコンで視線入力の設定をできる人も少なく、母が誤った入力をしてしまうことも多かったりして、意思確認のもと数ヶ月で使うのを断念しました」
進行性の難病を抱える家族がいる身としては、「もっと早く視線入力装置があることを知りたかった」という思いがある。そうしたら、もっと長く母と豊かな会話ができたかもしれない。
「今は視線入力装置にも色々種類があることを知ったんです。あの時、一つの装置でうまくいかなくても、別の装置を試せばうまくいったのかもしれない。視線入力とボタンを組み合わせた装置もできています。もしかしたらいまだに知らない装置があるのかもしれません」
周りの医療者や介護事業者からは、そうした生活を充実させるための介護テクノロジーなどの情報提供はあまり受けたことがない。
「補装具や介護用品に関してはケアマネさんやリハビリの方に教えてもらったのですが、特に民間の社会資源については全然情報が入ってきませんでした」
幼い頃からパソコンやスマホが当たり前にあった自分でさえ、難病患者が必要な情報に行き着くのにこんなに苦労しているのだから、そうでない当事者や家族はもっと苦労しているだろう。
この問題意識を持った自分が何か役立つ仕組みを作れないか。
そんな気持ちが徐々に芽生えていった。
(続く)
医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績